【2025年12月更新】デイサービス向けの行政最新情報まとめ
介護保険法
2025/12/05
介護保険法
ADL維持等加算
更新日:2025/08/04
【令和6年報酬改定対応】ADL維持等加算は、バーセルインデックス(BI)を用いて一定水準ADLの維持・改善につながった利用者が多い通所介護事業所が評価されるインセンティブ加算です。本記事ではADL利得の計算方法などをご紹介します。
この記事の目次
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから

ADL維持等加算の計算は、以下のように2段階に分かれています。
今回の記事ではそれぞれの計算方法を流れに沿って解説します。
また、最初に計算するADL利得の計算にはBarthel Index(BI:バーセルインデックス)が必要です。BI値について知っておく必要がありますので、まずはそこから解説していきます。
参照: よくわかる!ADL維持等加算の算定要件【2021年介護報酬改定】
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
バーセルインデックスとは、病気や障がいを持つ方、要介護者などのADL(日常生活動作)を評価する簡易的な指標の一つ。アメリカの理学療法士であるバーセル氏によって開発されたので、氏の名前を冠した評価名となっています。
評価指標が細かくないため、誰でもすぐに評価が可能です。そのため、利用者の全体像の把握も容易にできます。「できるADL」を評価する点が特徴で、世界共通のADL評価手法です。
バーセルインデックスの詳しい特徴・評価基準などは、以下の記事でご確認ください。
▶バーセルインデックスとは?特徴や評価項目・評価基準など徹底解説
ADL維持等加算は、2021年度の介護報酬改定前まではバーセルインデックスを計測できる者を機能訓練指導員に限っていましたが、計測するのは“適切に評価できる者”に変更になっています。
“適切に評価できる者”とは、具体的にはバーセルインデックスの測定方法に係る研修を受講したり、厚生労働省が作成予定のマニュアル及びバーセルインデックスの測定についての動画等を用いて測定方法を学習したりした者です。
厚労省が以下のQ&Aを出しているので、詳細を知りたい方はご確認ください。
(問5) ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」と いう。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。
(答)
・ 一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講する ことや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル(https://www.mhlw. go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)及びBIの測定についての動画等を用いて、 BIの測定方法を学習することなどが考えられる。
・ また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することな どによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでBI による評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の 同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。
参照:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)」(介護保険最新情報Vol.965)
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
ADL維持等加算のアウトカム指標には、バーセルインデックスを活用することが決められています。
バーセルインデックスの評価表は10項目で構成されています。内訳は食事・移乗・整容・トイレ・入浴・歩行(移動)・階段昇降・更衣・排便・排尿です。自立度合いに応じて各項目を15点・10点・5点・0点で評価します。
採点の合計は100点満点なのでとても把握しやすいです。満点の100点で全自立、85点以下で介助を必要とするが程度が少ない、60点以下だと起居動作に介助が必要、40点以下はほとんどの動作に介助が必要、20点以下で全介助が必要という基準になっています。
バーセルインデックスの評価項目について、さらに詳しく解説しているのは以下の記事です。ぜひ参考にしてください。
▶バーセルインデックスとは?特徴や評価項目・評価基準など徹底解説
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
要介護者の1年間のADL値を集計した評価結果で加算の可否が決まるのがADL維持等加算です。
維持、あるいは改善している結果が得られた場合は評価期間終了後の1年間、要介護者の全利用者に対して加算が可能です。2021年度の介護報酬改定で、算定要件が緩和され、単位数も10倍に引き上げられました。また、2024年度の介護報酬改定では、ADL利得の条件の変更や計算方法の簡素化が行われました。ここではADL利得の計算対象者、計算方法や計算式を解説します。
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
ADLの評価方法や項目・書き方などの基本的な情報は、以下の記事を参考にしてください。
▶ADLの評価方法とは|介護・看護・医療で把握する目的・項目や書き方を徹底解説
ADL利得の計算対象者は休んでいる期間を除き6ヵ月以上サービスを利用している方のみです。また、ADL利得の計算の対象になるかわからない場合でも、必ず決められたタイミングで情報を提出しなければなりません。決められたタイミングとは、利用開始月と開始月から起算して7ヵ月目(7ヵ月目にサービスの利用がない場合は利用があった最終月)です。
では、下記の表で具体的に計算対象になるケースと、対象にならないケースをそれぞれ見てみましょう。利用者A,B,C,Dは計算対象者になります。一方、E,F,G,H,I,Jは対象外です。詳細は以下に記載していますので、ご確認ください。
利用者A,B,C,D:計算対象者
・初月と7ヵ月目に情報を提出済
・6ヵ月以上サービスを利用している
利用者E:計算対象外
・7ヵ月目にBI値の評価・提出がない
利用者F:計算対象外
・評価期間中に6ヵ月のサービス利用がない
利用者G,H,I,J:計算対象外
・7ヵ月目にBI値の評価・提出がない
・評価期間中に6ヵ月のサービス利用がない
※注:下記厚生労働省の表の赤枠内では利用者E,G,H,I,Jが「6月目にBI値の評価・提出がない」となっていますが、本記事では開始月から起算しているため「7ヵ月目」と表記しております。
参照:ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き(厚生労働省)

続いてADL利得の計算方法について解説します。計算方法は「7ヵ月目のBIの合計値ー初月のBIの合計値+調整係数」です。
初めに一人ひとりの利用者ごとに「7ヵ月目のBIの合計値」から「初月のBI値」を差し引いた値を出してください。続いて、上記の調整係数表の条件を踏まえて、それぞれの利用者の初月のADL値がどれに当てはまるかを確認しましょう。最後に該当している調整係数(0〜3いずれか)を加えると利用者ごとのADL利得が算出されます。
イメージが掴みやすいように具体的な計算例を紹介します。
例)7ヵ月目 初回 調整係数 ADL利得
70点 ー 60点 + 2 = 12
7ヵ月目 初回 調整係数
10点 ー 10点 + 1 = 1
初回と7ヵ月目でADLの評価結果が同じだった利用者のケースでもADL利得の平均値は1以上です。ADL維持等加算では、ADLを維持した事業者も評価する仕組みとなっています。
ADL維持等加算を算定するためには、全利用者のADL利得を出し、その上で全体の平均値を算出する必要があります。
ここでは、全利用者20人のケースで全体の平均値、ADL利得の出し方を解説します。
ご自身で計算をしなければいけないと不安に感じた方もいるかと思いますが、LIFEに提出をすることで計算は自動で行なわれるので、ご安心ください。
| 評価対象利用者のADL利得の平均値 | 加算算定 |
|---|---|
| →1未満 | ADL維持等加算 算定できず |
| →1以上 | ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月 |
| →3以上 | ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月 |
全利用者(上位と下位のそれぞれ1割を除く)のADL利得の平均が算定条件を満たしているかどうかの確認方法を解説します。条件に当てはまる場合は、その後1年間全ての要介護の利用者に対して算定が可能です。再度にはなりますが、ご自身で計算しなくともLIFE上で確認ができるので、ご安心ください。
前述のADL利得の全体の平均値は「5.6」でした。上記の表に記載されている加算算定条件「3以上」に該当しています。ADL維持等加算(Ⅱ)に該当しているので、利用者1人につき60単位/月が1年間算定可能です。初月と7ヵ月目のバーセルインデックスに変化があまり見られなかったり、維持されていたりする場合でもADL利得の平均が3以上になることもあります。
令和6年度の介護報酬改定により、これまでのADL値(バーセルインデックス)に加えて、「要介護度」「障害高齢者および認知症高齢者の日常生活自立度」「評価日」「初月対象又は6月対象への該当」を追加で提出することになりました。
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから

厚生労働省や各地方自治体より報告されているADL維持等加算に関するQ&Aに加え、実際に多くの通所介護事業所からリハブクラウドへ寄せられた「よくある質問」とその回答をご紹介します。
(問)これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定しようとする場合の届出は、どのように行うのか。
(答)
・令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始使用とする月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。
・令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報Vol.952)
(問)LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。
(答) 令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するBarthel Indexは合計値でよいが、令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、Barthel Indexを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報Vol.952)
(問)これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目の値で評価していたが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目となったのは、後の月が1月ずれたということか。
(答)貴見のとおり。引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報Vol.952)
(問)ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。
(答) ・一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)およびBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。・また事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある、加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。引用:(行政情報)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)(介護保険最新情報Vol.965)
(問)令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
(答)令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
① 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
② 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
ー 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
又は
ー 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前に同意を得る必要がある。
・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。
問 176 ADL 維持等加算(Ⅱ)について、ADL 利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL 利得3以上である必要があるか。
(答)令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL 利得が3以上の場合に、ADL 維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。
ADL維持等加算の「申出期限」は、ADL維持等加算の算定を前提に評価対象期間を開始することを自治体に申出する期限のことです。
ADL維持等加算の評価対象期間は、「加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間」と定められています。
ADL維持等加算の「算定を開始する場合の届出期限」とは、評価期間の終了月にADL維持等加算の要件を満たしていて算定を開始する場合に、自治体に届け出する期限のことです。
初月に利用がなかったご利用者の評価について、明確なケースが示されているわけではないのですが、利用開始月(再開)した時に評価してその翌月10日までに情報提出するという形で良いのではないかと解釈しています。詳細は自治体へ確認をお願いいたします。
利用者様が体調不良にて休まれていることが続いて評価が困難な際は、ADL維持加算が評価できない場合は利得計算の対象外になります。
Barthel Indexでは、「椅子とベッド間の移乗」ではなく、「車椅子とベッド間の移乗」として評価するよう定められています(LIFEの利活用の手引きに基づく)。そのため、評価時には車椅子を使用している前提で実施し、データ提出してください。
今回は、ADL維持等加算の具体的な計算方法についてご紹介しましたが、実際の計算や集計作業はLIFEのシステム内で行います。そのため、介護事業者が集計作業をする必要はありません。
前提として、ADL利得の計算対象者は6ヵ月以上サービスを利用している方と、利用開始月と開始月から起算して7ヵ月目に情報を提出している方に限られます。初月と7ヵ月目のバーセルインデックスに変化がない場合でも、ADL利得を得られるので積極的に算定することをおすすめします。
ADL維持等加算は事業所の成果を大きく評価する加算なので、ケアマネジャー様への営業や、利用者様や利用者様のご家族との関係性構築にも有用です。加算を検討されている方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
ADL維持等加算の算定要件と算定の流れを知りたい方に、無料で解説資料をプレゼントしています。
⇒資料のダウンロードはこちらから
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。

介護保険法
2025/12/05

介護保険法
2025/11/06
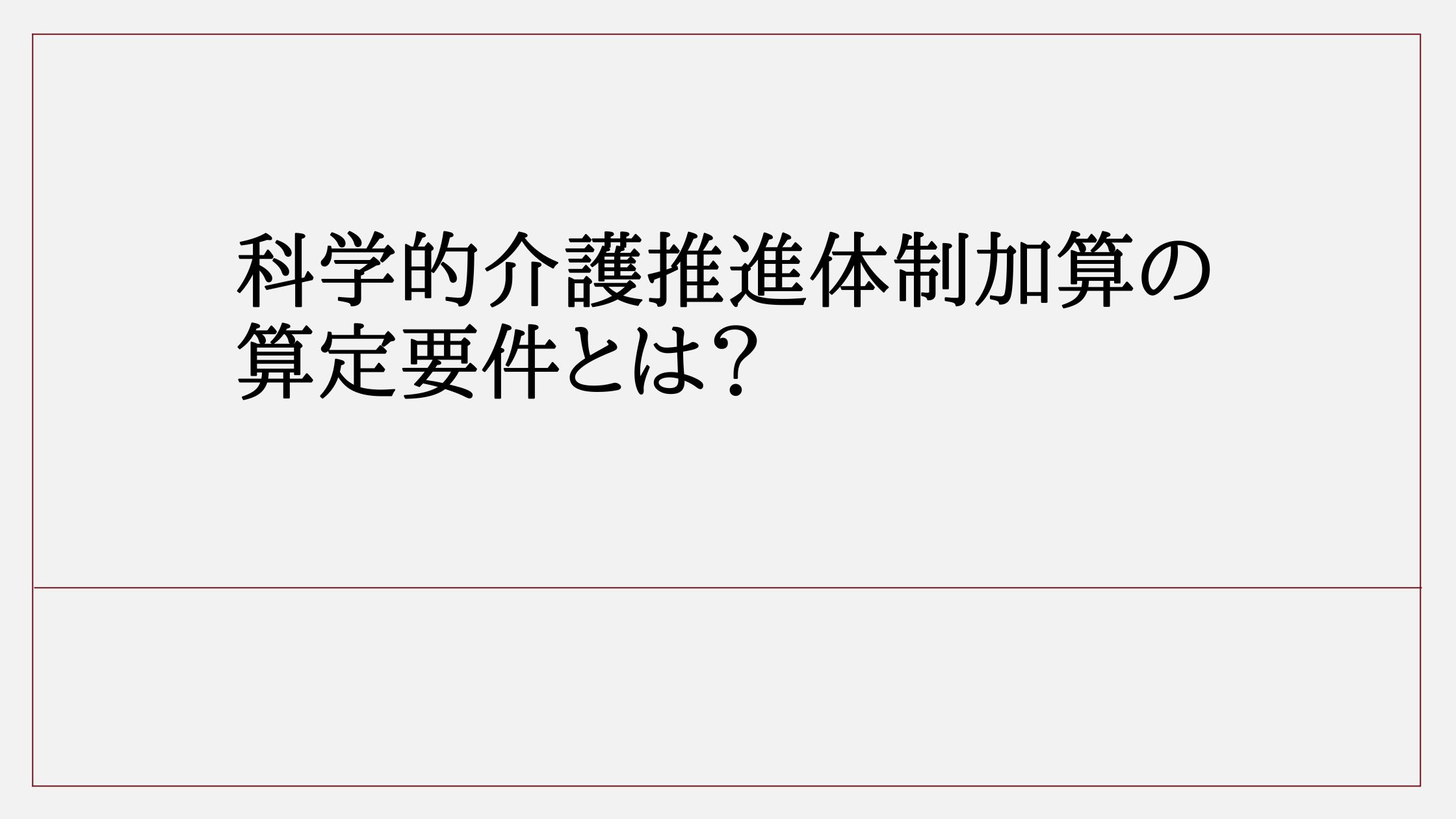
介護保険法
2025/10/24

介護保険法
2025/10/09

介護保険法
2025/10/09

介護保険法
2025/10/09