【2025年12月更新】デイサービス向けの行政最新情報まとめ
介護保険法
2025/12/05
介護保険法
介護報酬請求
更新日:2025/04/11
過誤請求とは、介護保険請求に誤りがあった場合に修正・再請求を行う手続きです。本記事では、過誤申立の流れや返戻との違い、過誤請求を防ぐためのポイントを分かりやすく解説。事業者やケアマネが押さえておくべきルールや期限についても説明します。
この記事の目次
介護保険制度において、サービス提供事業者が保険請求を行う際には、正確な内容と手続きが求められます。しかし、入力ミスや確認不足により、誤って請求してしまうこともあり得るでしょう。このような請求の誤りを「過誤(かご)」と呼びます。過誤があった場合、事業者は保険者や支払機関に修正を申し出て、適正な金額での請求をやり直す必要があります。
ここでは「過誤」「過誤申立」「過誤請求」の基本的な用語の意味と、その仕組みについて解説します。
過誤とは、審査決定済みの請求に誤りがあった状態を指します。たとえば、サービス提供日を誤って入力したり、提供していないサービスを請求してしまった場合などが該当します。
重要なのは、支払いが確定した後の請求に対してのみ過誤処理が適用されるという点になるでしょう。審査前や返戻になった請求には、過誤ではなく再請求を行います 。
過誤が発覚した場合、事業者はその請求を一度取り下げ、改めて正しい内容で請求し直す必要があります。
過誤申立とは、誤って行った介護給付費の請求を正式に取消すために行う手続きです。事業者はまず、保険者に過誤の申立書を提出し、保険者が国保連合会へその情報を送付します。
この申立は、原則として事業者自身が自主的に行うものですが、保険者からの指摘を受けて行うケースもあるでしょう。
申立が受理されると、国保連合会において過誤処理が行われ、介護給付費過誤決定通知書が事業所へ送付されます。その通知を確認後、正しい内容で再請求を行います。
過誤請求とは、誤った内容で介護保険の給付費を請求してしまった状態、またはその訂正に関わる一連の再請求処理全体を指します。誤請求に気付いた場合は、まず過誤申立を行い、支払機関にて当該請求を取り下げた後、改めて正しい内容で請求し直す必要があります。
つまり、過誤申立は取り下げの申し出手続き、過誤請求は実際の誤請求や再請求に関わる全体の流れを含む用語と言えるでしょう。
過誤請求の仕組みは単にミスを訂正するだけでなく、支払機関や保険者とのやり取り、そして期限管理が重要なポイントとなります。たとえば、申立が受理された後に一度請求が取り下げられた状態となり、その後正しい内容で再度請求書を提出する必要があります。
この仕組みは「誤りがあった場合にも正しい支払いを行えるようにする」という介護保険制度の透明性と公正性を保つために用意されているのです。
多くの場合、請求事務の煩雑さや人的ミスが原因であり、事業者にとっては時間的・金銭的なロス、さらには信頼の低下を招く可能性は否定できません。ここでは、よくある過誤の事例と、その影響について詳しく解説します。
過誤請求は、以下のような入力ミスや事務処理の不備により発生します。
| サービス提供日や内容の誤記入 | 実際には3月10日に訪問介護を提供したにもかかわらず、請求書には3月11日と記載してしまうと、実績と請求が一致せず過誤となります。提供したサービスが「身体介護」であったのに「生活援助」として入力した場合も同様です。 |
|---|---|
| 請求単価の誤り | 報酬改定後に新単価が反映されていない状態で旧単価のまま請求してしまうケースがあります。これは請求額の過不足を引き起こし、過誤処理の対象となります。 |
| サービス提供回数や時間数の誤申請 | 週2回のデイサービス利用を、誤って週3回で請求したり、訪問リハビリを15分提供したのに30分として入力してしまったりするなど、時間や回数の誤りが過誤処理の対象になります。 |
| 加算の誤適用 | 実際には加算要件を満たしていないにもかかわらず、認知症加算や特定処遇改善加算などを請求してしまうケースです。たとえば、認知症高齢者の日常生活自立度が基準に達していない利用者に加算を適用した場合、過誤と判定されるだけでなく、不正請求と見なされ、指導や監査の対象となる可能性があります 。 |
過誤請求が発生した場合、その影響は事業者と利用者の双方に及びます。ここでは、それぞれの立場から見た影響を整理します。
【事業者への影響】
| 事務負担の増加 | 過誤が生じると、過誤申立書の作成・提出、市町村とのやり取り、再請求書の準備など、通常業務に加えて多くの追加作業が必要になります。 |
|---|---|
| 資金繰りの悪化リスク | 過誤分の請求は翌月以降の請求から差し引かれる形で調整されるため、再請求が間に合わないと入金が遅れ、特に小規模事業所にとっては資金繰りへの影響が懸念されます。 |
| 未調整過誤と返金対応 | 再請求が漏れたり不備があった場合、未調整過誤として現金での返金が求められることがあります。これは事業所の財務に直接的な負担を与えます。 |
| 行政からの指導・監査リスク | 同種の過誤が繰り返されると、保険者や自治体からの信頼を損ない、改善指導や監査の対象になる可能性があります。 |
【利用者への影響】
| サービス提供の見直しリスク | 加算の過誤請求などが発覚した場合、一部のサービス内容やケアプランの再調整が必要になることがあります。これにより、利用者が受けているサービスの質や内容が一時的に変わる可能性があります。 |
|---|---|
| 自己負担額の過不足 | 請求ミスにより、利用者に一時的な過剰請求や不足請求が発生することがあります。後日、返金や追加請求が生じることで、利用者や家族に混乱や不安を与えるおそれがあります。 |
| 事業者への信頼低下 | 過誤請求が続くと、利用者やその家族から不信感が生じることがあります。信頼関係が重要な介護サービスにおいては、こうした印象の悪化が利用継続に影響する可能性もあります。 |
事業所がミスに気づいた際は、速やかに「過誤申立」を行い、保険者(市区町村)や国民健康保険団体連合会(国保連)と連携して対応を進めていく必要があります。ここでは、過誤請求が発生した際の一連の流れと、返戻との違い、過誤調整の種類についてわかりやすく解説します。
過誤請求が発生した場合、介護サービス事業所は過誤申立という手続きを行い、誤った請求の取り下げと正しい請求への差し替えを行う必要があります。過誤処理は、一般的に以下のような流れで進みます。
| ステップ1 | 事業所が保険者(市区町村)に対して過誤申立書を提出します。これは、すでに提出された請求に誤りがあったことを訂正するための公式な申し出となります。 |
|---|---|
| ステップ2 | 保険者が申立書の内容を確認し、国民健康保険団体連合会(国保連)に対して過誤処理の依頼を行います。 |
| ステップ3 | 国保連は過誤処理を実施し、その結果を過誤決定通知書として保険者を通じて事業所に通知します。これにより、当該請求の取り下げが正式に認められます。 |
| ステップ4 | 事業所が通知を受けた後、正しい内容で再度請求を行います。 |
最後に、国保連が再請求の内容を確認し、問題がなければ介護報酬が支払われるという流れになります。
返戻と過誤請求は、どちらも請求内容に修正が必要な場合に発生しますが、対応のタイミングや方法に明確な違いがあります。
返戻とは、国保連での審査段階で請求に不備や誤りが見つかった際に、審査が確定する前に請求データが差し戻されることを指します。この場合は、修正後に再度請求を行うことで対応できるでしょう。
一方の過誤請求は、すでに審査が完了し、介護報酬が確定・支払済みとなった後に誤りが発覚したケースです。この場合は、過誤申立を通じて一度支払いを取り消し、正しい内容で再請求を行う必要があります。
つまり、返戻は審査前の修正、過誤請求は審査後の修正という違いがあります。
過誤調整には、主に通常過誤と同月過誤の2つの種類があります。
通常過誤とは、過誤申立を行った月と再請求を行う月が異なる場合です。たとえば、4月分の請求に誤りがあり、5月に申立・再請求を行うといったケースが該当します。この場合、再請求後の入金が翌月以降になるため、介護報酬の入金が遅れるという影響が出ることがあります。
一方、同月過誤は、過誤申立から再請求までを同一の請求締切期間内で完結するケースです。取り下げ分と再請求分が同月に処理・相殺されるため、資金繰りへの影響が少なくて済むでしょう。
ただし、同月過誤を希望する場合は、保険者に事前相談が必要です。保険者の対応や締切期日によっては、同月過誤が認められない場合もあるため注意が必要です。
過誤が発生すると、再請求に多くの時間と手間がかかるだけでなく、事業所の信用にも悪影響を及ぼします。ここでは、過誤請求を未然に防ぐためのチェックリストと、日常業務で実践できる改善ポイントについて解説します。
参考:介護給付費請求の手引き 青森県国民健康保険団体連合会介護保険課
過誤請求を防ぐには、日々の業務の中でミスを減らす仕組みを整えることが重要です。以下の確認ポイントを日常的にルーチン化することで、ヒューマンエラーの発生を大幅に抑えることができます。
請求に使用する利用者情報に誤りがあると、請求内容全体が不正確になります。特に注意すべきは、氏名・被保険者番号・サービスコードの誤入力です。
また、サービス提供の内容や日数が正確に記録されているかも重要になるでしょう。実施記録と請求内容を照らし合わせる確認工程を必ず設けることが大切です。この工程を怠ると、未提供のサービスを請求してしまうなどの重大な過誤につながる可能性があります。
サービスの単位数や加算の有無によって、利用者の自己負担額や国保連への請求額が変動します。特に地域加算や介護職員等処遇改善加算などは、条件が複雑なため設定ミスが生じやすい項目になるでしょう。
基本単位数と加算を誤って組み合わせると、請求全体が無効になり、事務作業の負担が大幅に増えることもあります。計算結果が正確かどうかを、目視確認や請求ソフトを用いた検算でチェックする習慣を持つと良いでしょう。
近年の請求ソフトには、整合性チェックやエラー検知の機能が備わっており、人間が見落としがちなミスを自動で検出できます。
たとえば「請求内容と実績の不一致」や「支給限度日数を超えたサービス提供」など、エラー表示が出た場合はそのまま無視せず、必ず原因を確認するようにしましょう。
このような請求ソフトのシステム活用は、ミスの早期発見と防止に非常に有効です。
過誤請求の発生を防ぐには、業務の質そのものを向上させる必要があります。ここでは、日常業務に取り入れやすく、かつ効果の高い改善策を紹介します。
一人で請求作業を行う場合、どうしても主観的なチェックになりがちです。そのため、必ず別の職員による確認工程を設けるダブルチェック体制が有効になるでしょう。
たとえば、初期入力は事務職員が行い、最終確認を管理者が行う、あるいはチェックリストを用いて交差チェックをするなどの方法があります。第三者の視点を入れることで、自分では気づけなかったミスに気づける可能性が高まります。
国保連合会(国保連)が発信する通知や手引きには、加算の取り扱い変更や様式の更新など、重要な情報が数多く含まれています。これを見逃すと、意図せず誤ったルールで請求してしまうリスクがあります。
「介護給付費等請求の手引き」や各都道府県の通知文書を毎月定期的に確認し、内容をスタッフ間で共有しましょう。情報収集と共有を担当する職員を決めておくことで、情報の漏れや見落としを防ぎやすくなります。
請求の根拠となるケアプランが適切であることを確認するには、ケアマネジャーとの連携が不可欠です。たとえば、支給限度額を超えたサービスを誤って請求してしまうケースでは、ケアプランの設定ミスや連絡不足が原因のこともあります。
そのため、月初や月末などのタイミングでケアマネージャーとこまめに情報のすり合わせを行うと良いでしょう。請求前にサービス内容・回数・加算の有無などを相互に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
介護保険制度における過誤請求とは、誤って請求してしまった内容を訂正するために行う「過誤申立て」と、その後に正しい内容で再請求を行う一連の手続きを指します。
この過誤申立ては、いつでも行えるわけではなく、各自治体が定めた期限内に提出する必要があります。提出が遅れると、再請求が翌月以降にずれ込み、事業所の資金繰りに影響を与えることもあります。過誤請求に関するルールと期限を正しく理解しておくことが重要です。
過誤申立ての締切日は、自治体(介護保険者)によって異なり、全国で統一されているわけではありません。
多くの自治体では「請求月の翌月20日頃まで」を締切としています。たとえば、4月分の請求に誤りがあった場合、その過誤申立ては5月20日頃までに提出する必要があるでしょう。
また、一部の自治体ではさらに細かく締切日を設定しており「〇月〇日までに提出されたものは翌月処理、それ以降は翌々月処理」といった運用を行っているケースもあります。
そのため、申立てのタイミングによっては再請求の処理時期が1ヵ月以上ずれることもあるでしょう。
加えて、電子申請と紙申請で締切日が異なる自治体もあるため、各自治体の公式ページや通知を事前に確認しておくことが大切です。
介護保険の請求には、法律上の時効も存在します。
請求できる期間は原則として2年間と定められています。2年を過ぎると、内容が正しかったとしても時効になってしまうため、注意しましょう。
この2年間は、サービスを提供した月の3ヵ月後の1日から起算されます。たとえば、2023年4月に提供したサービスは、2023年7月1日から起算し、2025年6月30日までが時効期間となります。
過誤申立てが受理された後、通常は翌月の介護給付費請求で再請求を行います。ただし、再請求できるのはあくまで過誤処理が完了した月以降となるため、過誤処理にかかる時間も考慮しなければなりません。
たとえば、月末近くに過誤申立てを提出した場合、処理が翌月に持ち越されることがあります。
その結果、再請求もさらに1ヵ月遅れることとなり、事業所にとって資金回収が遅れるリスクが生じます。
このような事態を避けるためにも、請求内容のチェック体制を強化し、誤りが見つかった時点で速やかに過誤申立てを行うことが重要になるでしょう。
介護保険請求における過誤請求は、誰にでも起こりうる業務上のミスですが、適切な対応と予防策によってリスクを大きく減らすことができます。
過誤申立の正しい流れや返戻との違いを理解し、日々の業務にチェック体制を組み込むことで、事業所の信頼性向上につながります。
請求のルールや期限を正確に把握し、組織全体でミスを防ぐ仕組みを整えていくことが重要です。丁寧な確認と職員間の連携を大切にしましょう。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。

介護保険法
2025/12/05

介護保険法
2025/11/06
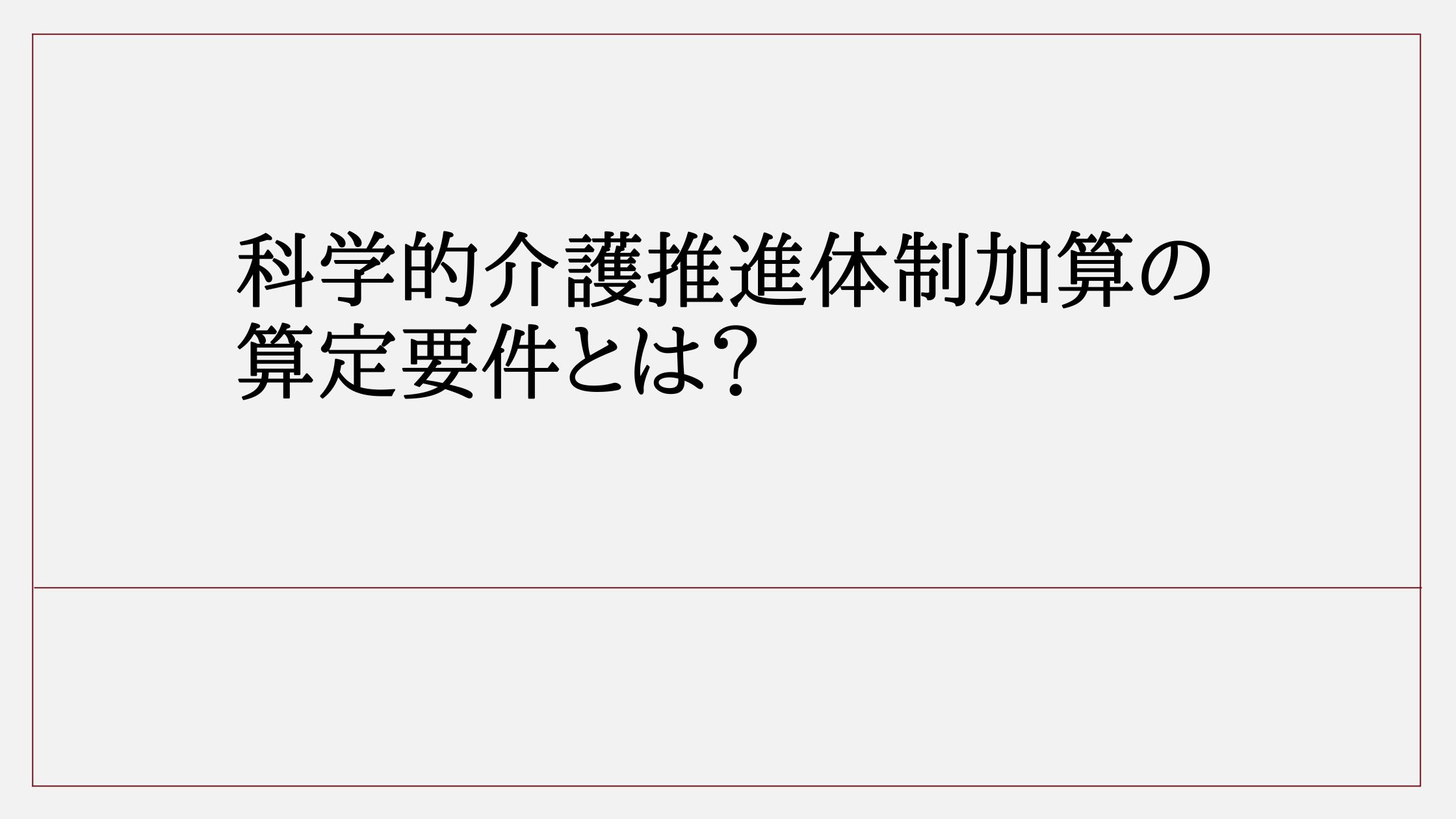
介護保険法
2025/10/24

介護保険法
2025/10/09

介護保険法
2025/10/09

介護保険法
2025/10/09