FIMで知っておきたい排泄コントロール(排尿・排便)の採点方法
現場ノウハウ
2025/10/14
現場ノウハウ
お役立ち情報
更新日:2025/03/14
介護現場でヒヤリハット、実際に利用者を怪我させてしまったらどうしますか? 初期対応や法的責任、再発防止策まで、介護職が知っておくべき情報を網羅的に解説。万が一の事故に備え、正しい知識を身につけて、利用者の安全を守りましょう。
この記事の目次
介護現場では、利用者の安全確保が最優先事項であることは言うまでもありません。しかし、事故の発生は依然として大きな課題となっています。特に、転倒や転落、誤嚥などの事故が数多く報告されています。
公益財団法人 介護労働安定センターが平成30年に発表した「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書によれば、介護現場で報告された276件の事故のうち、約65.6%が転倒・転落・滑落、13.0%が誤嚥・誤飲・むせこみ、2.5%が送迎中の交通事故が発生しました。
【厚生労働省報告 276事例 事故状況分類】
| 事故の種類 | 割合(%) |
|---|---|
| 転倒・転落・滑落 | 65.6 |
| 誤嚥・誤飲・むせこみ | 13.0 |
| 不明 | 12.0 |
| その他 | 5.8 |
| 送迎中の交通事故 | 2.5 |
| ドアに体を挟まれた | 0.7 |
| 盗食・異食 | 0.4 |
参考:「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書
また、これらの事故による傷病分類では、骨折が70.7%、死亡が19.2%を占めています。このデータは、介護現場での事故が利用者に重大な影響を及ぼす可能性があることを示しています。
【厚生労働省 276事例に関する介護事故の傷病分類】
| 傷病分類 | 割合(%) |
|---|---|
| 骨折 | 70.7 |
| 死亡 | 19.2 |
| あざ・腫れ・擦傷・裂傷 | 2.5 |
| 脳障害 | 1.1 |
| その他不明 | 6.5 |
参考:「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書
上記の「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書のデータは、重大事例(概ね30日以上の入院を伴う事例)が対象になっています。
よって、ここで示したデータにおいては、事故が発生したからといって必ずしも高確率で骨折や死亡につながるという内容ではありません。しかし、以上のデータから介護現場では転倒・転落や誤嚥といった事故が起きやすく、これらが骨折や死亡といった重大な結果を招く可能性が高いことが分かります。
介護現場では、日々の業務において利用者の安全を確保するため、環境整備や適切な介助、見守りの強化などの対策を講じることが重要なのは言うまでもありません。その中でも、特に重大な事故を予防することが大切になるでしょう。
介護現場では多くの事故が発生していますが、特に 転倒・転落・滑落、誤嚥・誤飲・むせこみ、送迎中の交通事故は、重大な影響を及ぼす可能性があるため、十分な対策が必要です。
事故の発生には 利用者の身体的要因・環境の問題・職員の対応などが複雑に絡んでおり、それぞれ適切な対策を講じることが求められます。
介護現場で最も多く発生する事故であり「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」の報告書では全体の65.6% を占めています。転倒や転落による骨折は、寝たきりや要介護度の悪化につながることが多いため、介護現場では特に注意が必要です。
この事故は、主に利用者の身体的な要因と環境的な要因によって発生します。
| 利用者の身体的要因 |
・筋力・バランスの低下:歩行時のふらつきが増え、つまずきやすくなる。 ・認知機能の低下:注意力が散漫になり、床の障害物に気付かず転倒することがある。 ・視力の低下:距離感や段差の認識が難しくなり、階段や浴室での転倒リスクが上がる。 ・薬の副作用:降圧剤・睡眠導入剤の影響でふらつきが生じることがある。 |
|---|---|
| 環境的要因 |
・床の滑りやすさ:適切な床材でないと、転倒のリスクが高まる。 ・手すりの未設置・不適切な高さ:支えがないとバランスを崩しやすい。 ・夜間の照明不足:暗い中での移動時に障害物が見えにくくなる。 |
食事中や服薬時に発生しやすい事故であり、全体の13.0% を占めています。誤嚥が原因で誤嚥性肺炎を引き起こすと、高齢者の健康状態が急激に悪化する可能性があります。
誤嚥や誤飲は、主に食事や服薬時の対応の問題と利用者の嚥下機能の低下によって発生します。
| 利用者の身体的要因 |
・嚥下機能の低下:加齢による筋力低下で、飲み込む力が弱くなる。 ・認知機能の低下:口の中の食べ物を適切に処理できず、誤って飲み込む。 ・姿勢不良:食事中に前かがみになりすぎると、気道に入りやすくなる。 ・薬の影響:鎮静剤や抗精神病薬が嚥下機能に影響を与えることがある。 |
|---|---|
| 環境・対応の問題 |
・食事形態が適切でない:固いものや粘り気の強い食べ物が誤嚥を引き起こす。 •食事介助の不足:食事中に適切な声掛けが行われていない。 •飲み込みの確認不足:食事の途中で口の中に食べ物が残ったままになる。 |
介護施設では、デイサービスや通院支援のために送迎車両を利用する機会が多く、送迎中の交通事故は全体の2.5%を占めています。一見少ない割合に見えますが、一度事故が発生すると 重大な怪我につながる可能性が高いため、注意が必要です。
送迎中の事故は、主に運転手のヒューマンエラーや利用者の動作の影響によって発生します。
| 運転手の要因 |
・運転手による判断ミス:介護業界ではスタッフの高齢化が進んでいることもあり、反応の遅れや判断ミスが生じることがある。 ・安全確認の不足:駐車場や施設前での発進時に、利用者や歩行者を見落とす。 ・過密なスケジュール:時間に追われ、急発進・急ブレーキが増える。 |
|---|---|
| 利用者の要因 |
・乗降時の転倒:車椅子や杖を使用する利用者が、無理に乗り降りしようとして転倒することがある。 ・車内での不適切な姿勢:座席のシートベルトが正しく装着されていないと、急ブレーキ時に怪我をするリスクがある。 ・認知症による突発的な行動:車内で突然立ち上がったり、ドアを開けようとすることで危険が生じる。 |
介護現場で利用者が怪我をした場合、迅速かつ適切な初期対応が求められます。対応が遅れたり不適切だったりすると、症状が悪化するだけでなく、事業所や介護職員の責任が問われる可能性もあります。
以下で、事故発生時の初期対応の方法と重要性について詳しく解説しますので、ご参考ください。
事故が発生した際は、まず 利用者の安全確保を最優先に行います。以下の点に注意しながら行動しましょう。
| 利用者の意識の有無を確認 | 声をかけて意識があるか確認します。意識がない場合は、直ちに救急対応が必要です。 |
|---|---|
| 出血や骨折の有無を確認 | 目視で出血や腫れ、異常な角度の関節などを確認し、必要に応じて応急処置を行います。 |
| 事故現場の安全確認 | 転倒や転落などの場合、再び事故が起こるリスクがないか確認し、必要なら環境を整えます。 |
| 利用者の移動は慎重に行う | 転倒・転落後、無理に起こすと症状が悪化する可能性があります。頭部を打った場合や骨折が疑われる場合は、動かさずに医療機関の指示を仰ぎます。 |
介護職員は医療行為を行えませんが、応急処置は業務の一環として認められています。怪我の種類ごとの対応を確認しておきましょう。
| 擦り傷・切り傷(軽度の出血) | 1. 清潔なガーゼやタオルで圧迫止血 2. 傷口を流水で洗浄 3. 消毒液を使用せず、清潔なガーゼで保護(必要なら絆創膏) 4. 大きな傷や深い切り傷の場合は医療機関へ連絡 |
|---|---|
| 打撲・捻挫 | 1. 患部を安静にする 2. 氷や冷却シートで冷やし、腫れや炎症を抑える 3. 内出血が広範囲に及ぶ場合や、強い痛みが続く場合は医療機関を受診 |
| 骨折が疑われる場合 | 1. 無理に動かさず、クッション等で固定 2. 医療機関へ連絡し、受診や搬送を手配 |
| 頭部を強く打った場合 | 1. 意識や反応の有無を確認 2. 嘔吐、めまい、頭痛、言葉のもつれがある場合は医療機関へ連絡 3. 外傷がなくても、しばらく状態を観察 4.時間が経過してから症状がみられた場合も医療機関へ連絡 |
| やけど | 1. すぐに流水で冷やす(15分以上) 2. 衣服が張り付いている場合は無理に剥がさない 3. 水ぶくれができたり、広範囲の場合は医療機関へ連絡 |
| 誤嚥 | 1. 利用者の様子を観察咳が出ている場合は、無理に介入せず、咳を続けさせて異物を排出させます。声が出ない・顔色が変わる・呼吸困難がある場合は、窒息の可能性が高いため、すぐに以下の対応を行います。 2. 背部叩打法利用者を前かがみにさせ、肩甲骨の間を手のひらの付け根で強くたたきます。(5回程度)これで異物が出ない場合は、次の方法を試します。 3. 腹部突き上げ法(ハイムリック法)※意識がある場合利用者を後ろから抱えるようにし、へその少し上をこぶしで押さえ、もう一方の手を上から重ねます。手前かつ上方向に素早く押し上げます。(5回程度繰り返す) 4. 意識を失った場合直ちに救急車を要請し、心肺蘇生を行う準備をする。 5. 医療機関への連絡異物が出た後も、誤嚥性肺炎のリスクがあるため、利用者の体調をしばらく観察し、必要に応じて医療機関へ相談します。 |
事故の規模によっては、医療機関への連絡や救急搬送が必要になります。以下の基準を参考に、速やかに判断しましょう。
| 症状 | 判断基準 |
|---|---|
| 意識がない・呼びかけに反応しない | ただちに119番通報し、救急搬送を要請する。 |
| 頭を強く打ち、嘔吐・めまい・意識障害がある | 119番に通報し、救急搬送が必要 |
| 出血が止まらない・傷が深い | 早急に医療機関を受診。必要なら救急外来へ。 |
| 骨折が疑われる | 動かさずに固定し、医療機関を受診。移動が困難なら救急搬送も検討。 |
| やけどが広範囲 | すぐに冷やし、医療機関を受診。重症の場合は救急搬送。 |
上記の表の説明は、一般的な判断基準になります。各個人のサービス利用状況によって細かな対応は異なる点にご注意ください。
たとえば、看取りのケアプランを立てていたり、訪問看護サービスが入っていたりするケースなど、それぞれの状況に応じた救急時の対応方法を決めていることがあります。
119番通報時は 「介護施設で利用者が〇〇(症状)を起こした」と簡潔に伝えるとスムーズに対応してもらえます。救急隊員の指示に従いつつ、施設の住所・利用者の年齢・性別などを間違えないように伝えましょう。
利用者の家族には 事実を簡潔に伝え、現状を正確に報告することが大切です。以下のような流れで連絡すると、適切な対応につながります。
家族へ連絡する際は、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
事故発生後は、正確な記録を残すことが重要です。記録が不十分だと、事故原因や再発防止策を検討する際に問題が生じる可能性があります。以下のポイントを押さえて記録しましょう。
介護現場で利用者が怪我をされた場合、初期対応だけでなく、その後の適切な対応も非常に重要です。以下に、事故後に取るべき具体的な対応手順を説明します。
介護現場で事故が発生した場合、その責任の所在は状況により異なります。以下に、介護施設や事業者、そして介護職員個人の法的責任について説明します。
介護施設や事業者は、利用者の安全を確保する「安全配慮義務」を負っています。利用者の生命や身体の安全を守るために必要な注意を払うことが求められます。たとえば、転倒のリスクが高い利用者に対して適切な見守りや環境整備を怠った場合、安全配慮義務違反と判断される可能性は否定できません。
事業者が「被用者の選任および事業の遂行について相当の注意を払った場合」または「損害が避けられないものであった場合」免責が認められる可能性があります。ただし、この免責が認められるケースは極めて限定的です。
介護職員個人が業務上の注意義務を怠り、利用者に損害を与えた場合「業務上過失致死傷罪」などの法的責任を問われる可能性は考えられます。もしも重大な過失や虐待が認められた場合は刑事責任が問われる可能性があるため、適切な対応が求められます。
ただし、介護事故の責任は原則として施設や事業者が負うことが一般的であり、職員個人が直接責任を問われるケースは稀です。実際には職員個人が直接責任を問われるケースは少なく、多くの場合、施設や事業者が責任を負うことが一般的でしょう。
損害賠償の主な内訳は以下のとおりです。
| 治療費 | 怪我の治療にかかる医療費 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 治療中の精神的苦痛に対する補償 |
| 後遺障害慰謝料 | 重度の後遺症が残った場合に支払われる慰謝料 |
| 逸失利益 | 事故によって被害者が将来得られたはずの収入(働いていた場合に発生) |
上記の損害賠償額は一例です。事故の状況や被害者の状態によって異なりますが、高額になるケースも少なくありません。そのため、施設や事業者は賠償責任保険に加入しておくことで、万が一の際の経済的負担を軽減できます。
報告書の内容が不十分だと、再発防止策の検討や責任の所在を明確にする際に問題が生じるため、正確かつ詳細に記載することが重要です。
事故報告書には、以下の項目を含める必要があります。
| 基本情報 | 事故発生日時、場所、関係者の氏名(職員・利用者) |
|---|---|
| 事故の詳細 | 発生状況、事故の原因、職員の対応 |
| 負傷の程度 | 利用者のケガの部位、状態、医療機関での診断内容 |
| 応急処置の内容 | どのような処置を行ったか(例:止血、アイシングなど) |
| 事故後の対応 | 家族や医療機関への連絡内容、事業者としての対応 |
| 再発防止策 | 事故原因の分析結果と、再発防止に向けた対策 |
事故報告書作成時には、以下の点に注意しましょう。
| 事実のみを記載 | 推測や主観的な意見を含めず、目撃した事実のみを記録する |
|---|---|
| 具体的に記載 | 曖昧な表現(「いつも通り対応していた」など)を避け、誰が、何を、どのようにしたのか明確にする |
| 誤字脱字を避ける | 内容が誤解を招かないよう、慎重に確認する |
| 迅速に提出する | 事故発生後、速やかに報告書を作成し、管理者に提出する |
介護現場では、事故の再発を防ぐための具体的な対策を講じることが重要になります。以下で、詳しく解説します。
リスクアセスメントとは、事故の発生要因を特定し、リスクを最小限に抑えるための対策を考える手法です。以下の流れで実施すると良いでしょう。
| 1.事故の発生状況を分析 | 過去に発生した事故やヒヤリハット事例を参考に、事故の種類や発生場所、原因を分析します。特に転倒や誤嚥、介助中の怪我などは、頻発しやすい事例として重点的に検討します。 |
|---|---|
| 2.リスクの洗い出しと評価 | 施設内の環境、職員の動き、利用者の身体状態を確認し、どこにリスクが潜んでいるかを洗い出します。その上で、発生頻度と影響度を考慮し、リスクの優先度を決定します。 |
| 3.予防策の検討と実施 | リスクの評価をもとに、具体的な予防策を考えます。たとえば、転倒リスクの高い利用者には歩行補助具を導入する、食事中の誤嚥防止のために食事形態を見直す、介助動作の標準化を図るなどの対応が考えられます。 |
| 4.定期的な見直しと改善 | 一度実施したリスクアセスメントは継続的に更新することが重要です。新たな事故やヒヤリハットが発生した際には、都度見直しを行い、事業所全体で共有します。 |
再発防止には、職員の意識向上とスキルアップが不可欠です。以下のような研修を定期的に実施することで、安全管理能力の向上が図れるでしょう。
| 事故発生時の初動対応訓練 | 転倒や誤嚥、急変など、実際に起こりやすいケースを想定し、職員が迅速に適切な対応をとれるようシミュレーションを行います。 |
|---|---|
| 介助技術の見直し | 移乗・移動介助、食事介助、入浴介助など、事故につながりやすい動作の見直しを行い、正しい技術を習得します。 |
| ヒヤリハット報告の共有 | 職員同士でヒヤリハット事例を共有し、事故につながるリスクを事前に把握できるようにします。これにより、個々の経験を施設全体で活かすことが可能になります。 |
| コミュニケーション能力向上 | 利用者の状態変化を見逃さないためには、職員同士の情報共有が重要です。報告・連絡・相談の徹底を図り、チームワークを強化します。 |
事故発生時の対応や日常の介助方法を標準化するためには、施設独自のマニュアルを作成することが有効です。作成する際には、以下のポイントを押さえましょう。
| シンプルでわかりやすい表現にする | 専門用語を多用せず、誰が読んでもすぐに理解できる内容にします。特に新人職員や派遣スタッフにもわかりやすいよう、簡潔な表現を心がけましょう。 |
|---|---|
| イラストや写真を活用する | 文章だけでは伝わりにくい介助方法や注意点については、図解や写真を用いると、視覚的に理解しやすくなります。 |
| 施設の実態に即した内容にする | 施設の構造や利用者の特性に合わせた内容に調整します。たとえば、認知症の方が多い施設では、認知症対応の注意点を重点的に記載するなどの工夫が必要です。 |
| 定期的に更新する | 事故報告書やヒヤリハット事例をもとに、マニュアルの内容を定期的に見直し、最新の情報を反映させます。 |
施設環境の見直しも、事故を防ぐためには欠かせません。以下のようなポイントに注目して改善を図りましょう。
| 転倒防止対策 | 床の滑りやすさをチェックし、滑り止めマットを設置する、手すりを増設するなどの対策を講じます。また、夜間の事故を防ぐために、廊下やトイレの照明を強化することも有効です。 |
|---|---|
| 動線の見直し | 施設内の移動ルートを確認し、歩行の妨げになるものがないかチェックします。特に車椅子利用者がスムーズに移動できるよう、通路の幅を確保することが重要です。 |
| 食事形態の適正化 | 誤嚥事故を防ぐため、利用者の嚥下機能に応じた食事形態を見直します。また、食事介助の際は、正しい姿勢を維持できるようサポートすることが必要です。 |
| 緊急対応設備の充実 | ナースコールや非常ベル、AED(自動体外式除細動器)などの位置を確認し、緊急時に迅速に対応できる体制を整えます。 |
交通事故の対策も欠かせません。以下のようなポイントに注目して改善を図りましょう。
介護現場では、事故を完全に防ぐことは簡単ではありません。ただし、正しい初期対応や報告手順を理解しておくことで、利用者の安全を確保し、介護職自身のリスクを軽減できます。利用者を怪我させてしまった際には、冷静に状況を把握し、適切な応急処置を行うことが重要です。
その後、医療機関への対応や家族への報告、施設内での事故記録を適切に進めることで、再発防止にもつながります。また、事故の責任範囲についても正しく理解し、法的リスクを回避するための対応を押さえておきましょう。
事故が発生しない環境づくりに加え、もしものときに適切に行動できるよう、知識と準備を整えておくことが重要です。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
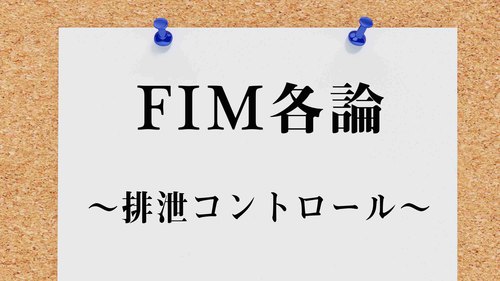
現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14
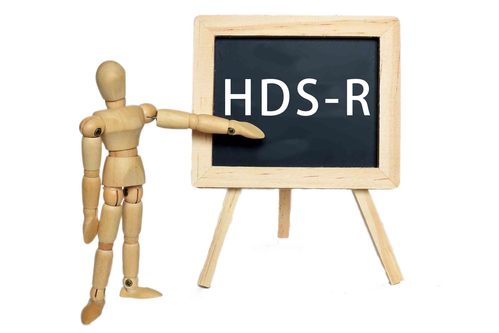
現場ノウハウ
2025/10/14