FIMで知っておきたい排泄コントロール(排尿・排便)の採点方法
現場ノウハウ
2025/10/14
現場ノウハウ
お役立ち情報
更新日:2025/01/27
ホスピタリティとは「思いやり」や「心からのおもてなし」の意味を表す言葉です。挨拶や食事のときの作法など、形や行動の良し悪しがある程度定まっていることは「マナー」といい最低限のルールです。ホスピタリティが高い・ホスピタリティに溢れる接客について、飲食店・レストラン、介護施設・病院、ディズニーなどでの事例を交えてご紹介します。
この記事の目次
⇒「職員の業務過多・残業の改善方法」解説資料のダウンロードはこちらから
ホスピタリティとは、「思いやり」や「心からのおもてなし」の意味を表す言葉です。英語では、hospitalityというスペルです。
ホテルなどのサービス業でよく取り上げられる言葉ですが、最近では医療現場や介護現場などでも頻繁にホスピタリティという言葉が使われるようになりました。
ホスピタリティ産業という言葉も新たにできていて、宿泊業、運輸業、旅行業、ブライダル、テーマパーク、空港など、特に人に接客するサービスを提供する業種のことを指します。近年は、教育、医療、福祉もサービス業として認知が進み、ホスピタリティ産業としての認識が拡大しています。これらの業種だとホスピタリティを活かせる仕事と言われてはいますが、その他、飲食業などその他の仕事でも、相手への思いやりやおもてなしは仕事の中で発揮できます。
ホスピタリティの類語であり、語源にも関連する「ホスピス(hospes)」には、「客人等の保護」という意味がありますが、医療用語としても使われています。医療業界でのホスピスとは、癌などの疾病の末期患者を受け入れて、その人らしさを保ちつつ、苦痛を少しでも和らげていくため、チームを組んでケアするという緩和ケアの概念です。
病院や介護の分野でホスピタリティを考えるとき、ホスピスの概念を用いながら考えると具体例を考えやすいかもしれません。
⇒「職員の業務過多・残業の改善方法」解説資料のダウンロードはこちらから
ホスピタリティと似た言葉に「マナー」という言葉があります。
挨拶や食事のときの作法など、形や行動の良し悪しがある程度定まっていることは「マナー」といい、相手に不快感を与えないために作られた最低限のルールです。
| 【関連記事】 ・介護職員の接遇とは おもてなしの心を表現する4つのポイント【基礎知識】 ・身だしなみ(外見)で第一印象をアップさせる方法 介護の接遇マナー ・挨拶の仕方やお辞儀で好印象を与える方法 介護の接遇マナー ・介護の接遇マナー向上 社会人としての 敬語の使い方 や 言葉遣い を解説 ・介護の接遇マナー クレーム・苦情対応の7つのテクニックと対応事例 |
しかし、マナーという暗黙のルールはTPO(時と所と場合)に応じて形式が決まっているのに対し、ホスピタリティは自分と相手の「心」の要素が加わります。
マナーを守って周囲に合わせることに加えて、相手の心の状態に合わせて、自分にできる個別的な配慮で、相手に心地良さや安心感をもたらし、感動的な対応として好印象を残していただくことがホスピタリティです。
サービスは、お客様から対価を得て提供する行為であり、提供する側と受ける側の間に主従関係が存在します。一方、ホスピタリティは、お客様への思いやりや心からのおもてなしを指し、見返りを求めずに行われます。サービスは、マニュアル化しやすく、一定の品質を保ちやすいというメリットがあります。しかし、形式的になりがちで、お客様の真のニーズに応えられない場合もあります。
ホスピタリティは、お客様一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応ができるというメリットがあります。しかし、マニュアル化が難しく、提供者のスキルに左右されるというデメリットもあります。
サービスとホスピタリティは、それぞれ異なる概念ですが、お客様満足度を高めるという共通の目的を持っています。サービスを提供する際には、ホスピタリティの精神を持って接することで、お客様との良好な関係を築き、より高い満足度を提供することができます。
おもてなしは、日本独自の文化であり、客人をもてなす心を表します。ホスピタリティは、より広義の概念であり、相手への思いやりや心遣いを意味します。
おもてなしは、事前に準備し、形式を重んじる傾向があります。一方、ホスピタリティは、その場の状況に合わせて、臨機応変に対応することが求められます。
おもてなしは、相手との関係性を重視し、親密な雰囲気の中で行われます。ホスピタリティは、相手との距離感を保ち、丁寧な対応を心がけます。
おもてなしもホスピタリティも、相手を思いやる心が根底にあります。しかし、文化的背景や表現方法が異なるため、場面によって使い分けることが重要です。
ホスピタリティという言葉はサービス業の会社だけでなく、病院や介護施設でも使われることが増えてきて、接遇マナーやホスピタリティ研修という内容も身近になってきました。
ホテルや介護施設などのキャッチコピーとしても「ホスピタリティの高いサービスで皆様をおもてなしいたします」や「ホスピタリティ溢れる介護サービスを提供します」などよく耳にするようになりました。
しかし、ホスピタリティの意味は「思いやり」「心からのおもてなし」だとわかっても、実際にどんなことをすればホスピタリティが高い、ホスピタリティが足りないと言われるのがわからないと人も多いと思います。日本ではディズニーランドやホテルなどのディズニーリゾートのホスピタリティの高さが有名ですよね。
ホスピタリティとは、どのような接客態度のことなのか、どのようなコンセプトでのサービスなのか具体的な事例を挙げてご紹介していきます。
ディズニーランドはホスピタリティが高く、魔法にかかったかのようにみんなが満足できるということで有名です。
ディズニーリゾートで話題になったホスピタリティの高さを感じる事例としては、ディズニーランドでお昼寝している子供を抱いて座っているお母さんがいたとき、ディズニーキャラクターがその子の周りで「シー」のポーズをして配慮したという話があります。キャラクターが居るとみんなキャーキャー楽しくなりますが、その楽しさは壊さずに、眠っているこどもやお母さんにも嫌な気持ちをさせずに配慮した演技をした心遣いは素晴らしいですよね。
広い意味でのホスピタリティの例になりますが、実はディズニーランドには、みんなが不快に感じてしまう「蚊」がいないということを知っていますか?誰もが夢の魔法にかかって楽しめるように、木や水を工夫することで、蚊がいない場所にしているというのです。
レストランや飲食店などでの食事では、食事を提供する側でもマナーが最低限のルールになります。例えば、衛生的なお盆や食器で運んでくることや、和食だったら味噌汁が右側でご飯が左、お箸の置き方は右が持つ側になるように…などです。
飲食店に行く目的は、主に美味しいご飯を食べること、一緒にいる人と快適な時間を過ごすことなので、食器が不衛生だったり、違和感のある食器の配置だったりすると不快であり、飲食店のマナーの欠如を感じてしまいます。
ホスピタリティという概念では、飲食の提供のサービスにプラスして、相手の気持ちや目的にあった思いやりや心遣いを提供します。
例えば、飲食店に来ていただいたお客さんがデートで来ている場合、ちょっといい感じのお席にお通しする、お料理を女性が大きな口を開けて食べずに済むように食べやすいサイズにカットする、男性がおどおどしていても女性に心配を感じさせないような態度で接客をする、苦手なものはないか確認するなどが具体的なホスピタリティある態度かもしれません。
おばあちゃんの誕生日で3世代で来ている場合の例だと、お孫さんの椅子や寝る布団、小分けの取り皿などを多めに用意して差し上げるなど、個別にその方の快適や安心につながるようなおもてなしを考えて行うということがホスピタリティ精神です。
飲食店の店員の立場で、他人のプライベートに深入りしすぎるのもホスピタリティに反す部分はありますが、相手の目的や立場、雰囲気に合わせて柔軟に対応できるとお客様に感動をお届けすることができます。
病院や介護施設などでは、接遇マナーという言葉がホスピタリティと合わせて使われています。病院での医療の提供や介護施設などでの介護サービスの提供は、計画に沿ってチームで行われます。医療や介護を必要とする患者や利用者は、身体的にも精神的も立場が弱くなりやすく、この業界では患者やご利用者に対して負い目や不快感などを与えずに、その人らしく発言や希望を言いやすいように接遇マナーに力を入れています。
疾病の末期の患者に行われる緩和ケア・ホスピスを例にすると、ベッドメイクや衛生保持など、リラックスできる心地よい環境を整えることに加え、その方の細やかな希望にできる範囲でお答えしたり、暖かくお話を聞いて寂しさや不安を減らせる思いやりや、見た目が気になる処置や症状で周囲からの目を気にしていることを感じたときに、相手の気持ちになってそっと声をかけてお聞きして位置を移動したりといったことなどがあります。
| 【関連記事】 ・高齢者のこころを動かす「化粧活動」の効果と注意点とは!? |
具体例は挙げましたが、ホスピタリティは相手への思いやりとおもてなしですが、いいことをしようと思って相手の気持ちを勝手に想像しすぎてしまい、本人に無断で望まないサービスや行き過ぎた配慮をするかもしれないという課題があります。また、業界全体でホスピタリティに溢れるサービス提供をしていると、業界のサービス水準が高まりますが、行き過ぎたサービスが当たり前になり、期待のハードルがどんどん上がってしまうという可能性も課題として認識する必要があります。
ここで紹介したホスピタリティの例が当てはまるケースもありますし、不快な気持ちにさせてしまうこともあります。ホスピタリティの事例やホスピタリティばかりを全面に押し出すと、本来の価値である思いやりやご配慮から離れてしまうので、注意も必要です。
ホスピタリティとは、相手への思いやりや心遣いを形にすることで、温かい雰囲気を生み出し、良好な人間関係を築くために欠かせないものです。ホスピタリティを身につけるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
相手の立場に立つことは、ホスピタリティの基礎です。相手の置かれている状況、感情、考え方を理解しようと努めることで、真に必要な配慮が見えてきます。例えば、困っている人がいたら、「自分だったらどんな助けが必要だろう?」と想像してみましょう。
相手が言葉に出す前に、ニーズを察知し、先回りして行動することが大切です。小さな変化も見逃さず、さりげなくサポートすることで、相手は安心感と心地よさを覚えます。例えば、レストランで食事をしている人が水を飲み干していたら、すぐに水を注ぎ足す、といった行動が挙げられます。
相手の良いところを見つけ、言葉で伝えることは、相手を尊重し、信頼関係を築く上で重要です。ただし、お世辞ではなく、心からそう思えることを具体的に伝えましょう。
相手の話を丁寧に聞き、理解しようと努めることは、相手への敬意を示し、信頼関係を深める上で大切です。相槌を打ったり、質問をしたりしながら、積極的に耳を傾けましょう。
ホスピタリティとはどんなことか、そしてホスピタリティの具体事例を紹介してみました。ホスピタリティはひとりひとりへの気持ちを込めたおもてなしです。いろいろな引き出しを用意しておき、活かせるときに活かせることがホスピタリティ精神として大切なことです。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
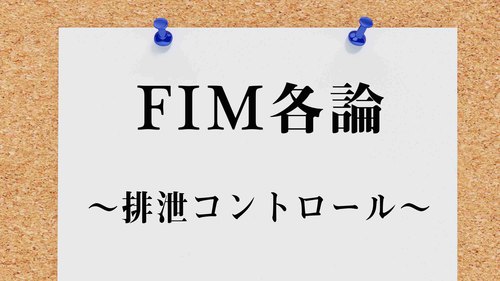
現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14
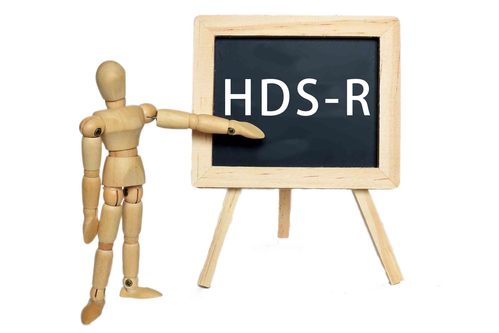
現場ノウハウ
2025/10/14