FIMで知っておきたい排泄コントロール(排尿・排便)の採点方法
現場ノウハウ
2025/10/14
現場ノウハウ
お役立ち情報
更新日:2025/05/16
デイサービスの業務効率化や業務改善のパフォーマンスを最大化するためには、団結力やモチベーション、満足度をあげることではありません。チーム全員が平等に発言できる仕組みを作れるかがポイントです。品質の良い一貫したサービスを創造するチームづくりを一緒に考えていきましょう。
この記事の目次
⇒「職員の業務過多・残業の改善方法」解説資料のダウンロードはこちらから

デイサービスの業務効率化を行うためには、必要最小限の能力でもうまくいくように、システム依存した事業を目指すことが重要です。そのためには「マニュアル」を作ることから始めましょう。
例えば、管理者は能力の高い従業員を好み、自身の業務を任せます。業務を任せられた従業員は初めのうちはやる気があって問題はないかもしれません。しかし、時間の経過とともに、仕事が雑になっていきます。
管理者は従業員のやる気を起こすために、ご機嫌とりをするしか方法はありません。それを見ている周りのスタッフはどう思うでしょうか?
管理者は好き放題している従業員のご機嫌をとり、注意すらできない。これでは、長期的に安定した結果を出し続けることは不可能になるでしょう。業務効率化どころか人間関係に亀裂が入ってしまう可能性もあります。
他にも、マニュアルをつくる理由があります。
それは、プロとしてのサービスの「一貫性」です。質の高いサービスを提供することはもちろんですが、それ以上に「同じサービスを提供し続ける」ことの方がもっともっと重要なのです。一貫性を保ちつつ、業務効率化を行っていくことが重要なのです。
例えば、私たちがスターバックスの美味しいフラペチーノを飲みに行くとしましょう。
店員さんは私たちを笑顔で迎え入れ、いつもと同じように注文し、いつもと同じようにお金を支払い、いつもと同じようにランプの下で待ちます。そして、いつもと同じように、落ち着いた雰囲気のソファーに腰掛けてフラペチーノを飲みます。
飲み終わったら、用意されているゴミ箱に捨て、お店をでます。この流れに一貫性がなかったら私たちはスターバックスにいくでしょうか?コーヒーの味が酸っぱくなったり、苦くなったり、店員さんのご機嫌が斜めだったり。私たちは多分行かなくなるでしょう。近くの別のお店に行ってしまいます。
デイサービスも同じです。ご利用者様は「いつもと同じように」一貫性のあるサービスを求めています。その仕組みづくりをすることが「マニュアルをつくる」ということなのです。
⇒「職員の業務過多・残業の改善方法」解説資料のダウンロードはこちらから

業務効率化のためのマニュアル作りは、業務内容をブロックごとにまとめ、その役割の業務分担をすることがマニュアル作りの基本となります。そして、現場で働いている従業員が結果に対して責任を負わされる仕組みをつくるべきです。
例えば、役割分担にコーヒーをつくるなどのカウンター作業があったとします。ある従業員は、日々のカウンター作業で必要最小限の仕事をします。他方ある従業員はコーヒーに可愛い付箋に一言メッセージで「今日もリハビリ頑張ってましたね」と伝える。
どちらがいいのでしょうか?
忙しい合間にそんなことできるか!と思われる方がもしいらっしゃれば、それは能率と効率を誤認している可能性があります。
デイサービスの主な目的は「ご利用者様の心を動かして体を動かすこと」これが基本です。来週もこのデイサービスに来たいと思ってもらえることが重要なのです。能率的に働くことは作業スピードは上がるかもしれませんが、Happyは提供できないのです。
マニュアルは貴社がご利用者様に提供している「クレド」に従います。それ以上はありえません。このクレドに対し「従業員が結果に対して責任を負わされる仕組みをつくる」ことが非常に重要な要素となります。
良い取り組みがある場合はマニュアル変更を含め、常にイノベーションを行える仕組みをつくる、そしてそれは常に現場発信であることが重要となります。

それでは、業務効率化を目的としたマニュアル作成する3つのステップをご説明します。イノベーションは絶えず繰り返しながらも、マニュアルをどんどん良いものにしていきます。「イノベーション→数値化→マニュアル化」のサイクルを一貫して行う組織体質を作り上げていきましょう。
| Step1 | 現場レベルでイノベーションを活性化 ・声かけや挨拶の方法を工夫してみる ・洋服を変えてみる ・送迎時の音楽を変えてみる ・配車の作り方を考慮する など思いつくこと全てを検証してみましょう。ご利用者様は常に見ています。答えはそこから判断できるでしょう。 |
| Step2 | 数値化してみよう ・業務の工夫をSNSやブログ、紙媒体のニュースレターにアップします。その結果、ご利用者様の紹介数が向上した ・洋服を変えることで、施設内のイメージが華やかになり、紹介者数が増えた ・ご利用者様の声が変わった など定性的な評価と定量的な評価を交え、評価を行っていきましょう。 |
| Step3 | マニュアル化 |
業務マニュアル作成のポイント:コミュニケーションを取りながら行うこと。
参照:【参考文献】マイケル・E・ガーバー著,原田喜浩訳(2008)『はじめの一歩を踏み出そう-成功する人たちの起業術-』世界文化社
マニュアルは業務の質を均一に保ち、スタッフ間の認識を共有するための大切なツールです。特に介護事業所では、誰が担当しても一定のサービス提供ができるように、実用的でわかりやすいマニュアル作成が求められます。以下では、具体的なマニュアル作りの手順を紹介します。
まずは「誰のために」「どのような場面で」「何を伝えるために」マニュアルを作るのかを明確にしましょう。たとえば「新入職員の入浴介助研修用」や「送迎時のトラブル対応フロー」など、対象や使用場面を限定することで、内容にブレがなくなります。
初めてマニュアルを作成する場合は、すでに存在する雛形や他施設の例を参考にすると効率的です。「介護マニュアル 作成 雛形」などで検索したり、業界サイトを活用したりするのがおすすめです。
手順は、①→②→③といった順序を明示し、箇条書きや図表を使って視覚的にも理解しやすくします。また、専門用語や抽象的な表現を避け、誰が読んでも同じ行動ができる内容を目指しましょう。
マニュアルの最後にはチェックリストを設け、実際の業務で確認しながら進められるようにすると実用性が高まります。チェックリストは、研修や評価のツールとしても活用できます。

では、上述したようなチームや組織づくりの工夫について考えます。
業務効率化を達成しパフォーマンスを最大化するためには、団結力やモチベーション、満足度をあげることではなく、チーム全員が平等に発言できる仕組みを作れるかがポイントです。
アレックス・ペントランドら(2015)の研究によると、最大限のパフォーマンスを発揮する集団の特徴として以下の3つを発見しています。
1つ目は「アイディアの多さ」
2つ目は「交流の密度の濃さ」
3つ目は「アイディアの多様性」
これらの要素をグループ内のメンバーが均等に発言していることとしています。
このようにデイサービスの業務効率化を行うためには、全てのメンバーが平等に発言する機会をつくる組織こそ、パフォーマンスの高いデイサービスを作れるのかもしれません。
参照:アレックス・ペントランド著,小林啓倫訳(2015)『ソーシャル物理学-「良いアイデアはいかに広がるのか」の新しい科学-』株式会社草思社

では、具体的にデイサービス業務のどの部分をマニュアル化するべきか一緒に考えていきましょう。デイサービスにおける業務負担割合で最も多いものが、圧倒的に大きいものが送迎。次いでレクリエーション・リハビリの準備、記録業務、直接介護業務です。これらについて一緒に考えていきましょう。
送迎は日々の業務ですので、最も重要なことは安全性への配慮を記載したマニュアルです。安全性を最大化するために、どうしたら良いかを常に考えましょう。送迎時のヒヤリハットはクリティカルな問題であり、1つ間違えば大事故になりかねません。ここを効率化することに大きな意味はありません。
一方、業務効率化できる部分は管理業務としての「配車管理表」。どういった道順で、どのご利用者様宅から伺うか。このような事務作業は早期にICT化し、効率化していきましょう。
レクリエーション(リハビリ業務も同様)のマンネリ化は、ご利用者様満足度の低下につながります。ご利用者様の満足度の低下はキャンセル率を高め、稼働率の低下につながります。稼働率が低下すると、営業利益も低下するため改善が必要です。
現場のスタッフの皆様は多種多様なバリュエーションを探しています。ここが現場レベルでの業務効率化の最大のポイントでしょう。
計画書や管理業務が大変という点は管理者のポジショントークであり、現場のスタッフからすると、レクリエーション素材を集める方が大変なのです。なぜなら、単発ではなく、毎日のことですから。
デイサービスではご利用者様のバイタル管理や入浴管理、機能訓練メニューの管理などを紙に記録していることでしょう。
しかし、その記録をタブレットに変更することで、業務効率が格段に上がります。業務日誌、介護記録、連絡帳に同期し、無駄な転記作業を効率化していきましょう。
スタッフにご高齢の方が多いので、できないと思っている管理者や経営者の方も多いのですが、今は簡単に誰でもできるデザインなので、昔と比べて使いやすくなっていますので、まずは試しにIT化を検討していくべきでしょう。
送迎やコアな介護業務以外は早期に効率化するべきです。特に考えなければならないのは、業務効率化をするべきところは、記録業務だけではないということ。
意外とスタッフが時間を費やしているところは、レクリエーションの準備やリハビリの準備です。個別のリハビリや運動が重要視されている現在、品質を保ちながら、効率化が必要なのです。

厚生労働省(2024)によると、介護職員が辞める理由ベスト3として
このように「職場の人間関係に問題があったため」を理由として辞める方が非常に多いのが特徴です。
皆様の職場はいかがでしょうか?
改善方法は以下の3つです。
デイサービスでは入浴やレクリエーション、体操、送迎、食事の準備など大まかな業務分担をしている介護事業所は多いでしょう。しかし、それだけでは全然役に立ちません。
なぜなら介護職は対人援助職であるが故に、洞察力が高い職員ばかりに仕事が増え、能力レベルが低い職員はずーっとご利用者と話し込んでいるからです。これでは、介護のプロとして質が低いと言っても過言ではないでしょう。
一人は頑張っていて、一人は喋っているだけ。それでは、ストレスがたまるのは当然です。しかし、喋ることが悪いわけではありません。なぜなら「ご利用者様と会話することは、サービスとして必要」だからです。だからこそ、明確な業務分担が必要なのです。
例えば、トイレ介助や移動介助のような利用者次第で突然必要になるコアな介護業務こそ、担当者を決めておくべきです。そうすることで担当になっている職員は、フロア全体を意識するようになります。そして、能力差が出にくくなるのです。
ポイント:コアな介護業務をマニュアル化し業務効率化をすることこそ、人間関係を改善させる第1歩です。
現場で働いていると何故か「声が大きい人の発言」や「責任者の発言」ばかりが尊重され、イチスタッフの声が反映されないことが多いです。これでは職員間の人間関係がよくなるはずがありません。
これは、特に管理者が意識して改善するべきです。一人一人の発言が尊重されているか。みんながしゃべりやすい雰囲気ができているか。話がしにくいのであれば、ラインのグループを作ったり、申し送りノートを作ったり、色々とできるはずです。
終礼で話しているじゃないかという人がいるかもしれません。そもそも、そこが間違っています。言葉を発することは得意不得意があります。勇気が必要なことだってあります。どのようにすれば、コミュニケーションが生まれやすくなるか。管理者が考えてください。
ポイント:「全てのメンバーが平等に発言できる環境」を作りましょう。
介助方法などの技術は経験値でカバーできます。しかし、そもそもご高齢者が苦手であったり、既存の職員と仲良くできない人を雇用すべきではありません。
質の低い人材をいくら教育したところで、結果は同じです。雇用する時点で「人柄を重視した採用」を検討することがもっとも良いのです。
ポイント:「人柄を重視した採用」をしよう
介護業界は常に人材不足です。長く働いてもらえる環境を作るためには、採用時の志望動機が重要です。個人の志望動機を達成できない事業所であれば、スタッフは必ずそれが理由で辞めていくでしょう。
参照:令和5年度介護労働実態調査介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書(2024年7月公益財団法人介護労働安定センター)

業務時間内での時間の使い方は、職員のモチベーションアップや業務効率化につながります。一方どこから着手すればよいか分からない人は多いのではないでしょうか? ここでは業務効率化を助ける方法と実践的アイデアをまとめ、解説します。
あなたが勤務している事業所では業務後に「終礼」を毎日行っていますか?その終礼は形が決まっていて、その日の個人に当てられた業務報告やヒヤリハットなど定例的に行っているのではないでしょうか?
コミュニケーションをとるために集まるのではないので、業務効率があがるとかご利用者様の求めるものにコミットするなど結果が出る「終礼」を目指します。
ポイント:終礼を見ればあなたの事業所の活性度がわかります
会議でよくあることですが、ただその日や月の報告のみをすることがあります。報告のみの会議は全く意味がありません。そもそもその会議には、パートタイムの人が参加していないことも多く、チーム全員がその場で共有するだけであれば、ノートやITを活用すれば十分なのです。
ではどうしたら良いのか。それは、あなたの事業所において「時間内に結論を出そう」と意識をまずは共有するべきでしょう。
事業所が安心安全でイキイキするための会議を目指し、会議自体のスキルを高めていくことが業務効率化につながるのです。無駄な話を徹底して省きましょう。
ポイント:時間内に結論を出すことをみんなで共有しましょう
報告事項や会議資料はすべて電子資料で共有することを目指しましょう。印刷用紙の節約になるだけでなく、各自が事前・事後の共有もしやすく、周知徹底しやすいメリットがあります。もちろん終礼などの会議に参加できていないスタッフが働きやすくなるメリットにつながります。
できればパソコンやタブレット、スマホでも対応可能なツールを活用することで、時間や場所に縛られることのない徹底したIT導入をオススメします。
ポイント:ITをなるべく導入し徹底して業務効率化を目指しましょう。
業務効率化のためのアイデアを有効活用して、ご利用者様の満足度を高める質の高い仕事を提供していく会議にしていきましょう。
結果としてあなたの事業所の評判は上がり、顧客獲得や従業員満足度は高くなるのです。業務効率化は内部でできる経営戦略、管理者が常に意識し、高みを目指しましょう。
| デイサービスの経営や運営は様々な視点から行っていくことが重要だといえます。これまでのやり方に加えて、稼働率アップさせるための営業戦略や、より業務効率化・生産性向上に貢献するITツールの導入などを検討していってもよろしいのではないでしょうか。 これら経営や運営に関する記事を一挙にまとめていますので、該当する記事を読んでいただき少しでも参考にしていただけたらと思います。 →→ 【完全保存版】デイサービス経営改善・運営・営業戦略・ITツール・実地指導・接遇に関する記事まとめ|随時更新 |
介護事業所の運営には、日常業務だけでなく、緊急時や問題発生時の対応まで見据えた各種マニュアル・指針の整備が欠かせません。これらの文書は、職員の行動を統一し、利用者の安心・安全を守るための「備え」として位置づけられています。以下では、厚生労働省が定める主な作成義務のあるマニュアルや指針について、その概要を簡潔にご紹介します。
利用者の急な体調不良や事故など、緊急を要する場面での初動対応を明確にしたマニュアルです。医師への連絡、救急要請、家族への報告など、職員が慌てず冷静に対応できるよう、対応手順を整えておきます。
サービス利用者やそのご家族から寄せられる苦情・不満に適切に対応するためのルールです。受付の方法から、対応記録、責任者による確認、再発防止の取り組みまで、一連の流れを定めます。
転倒や誤嚥、誤薬など、事業所内で発生しうる事故への対応を体系的にまとめたものです。発生時の対応はもちろん、関係者への報告、記録の取り扱い、再発防止のための検討会の実施などが含まれます。
職員間、または職員と利用者・家族との間に生じうるハラスメント行為(パワハラ・セクハラなど)を防止するためのマニュアルです。相談窓口の設置、早期発見・対応、職員研修の実施などがポイントです。
火災、地震、水害など、災害時の避難・誘導方法、安否確認、非常用物資の準備などについて定めた対応手順です。特に高齢者施設では避難に時間がかかるため、事前準備と訓練が重要です。
インフルエンザやノロウイルス、新型コロナウイルスなどの感染症に対する予防措置と、発生時の適切な対応策を定めた指針です。手指衛生、マスク着用、消毒、ゾーニングの方法などが記載されます。
高齢者虐待の未然防止・早期発見・迅速対応を目的とした指針です。身体的虐待だけでなく、心理的虐待やネグレクトも含めた広い視点での対応が求められ、職員教育や相談体制の整備も不可欠です。
自然災害や感染症など、有事においても介護サービスを途切れさせないための業務継続計画です。職員体制の見直しや、サービス優先順位の設定、代替手段の検討などを通じて、最低限の事業継続を図ります。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
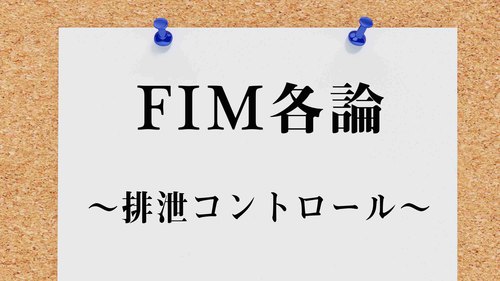
現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14
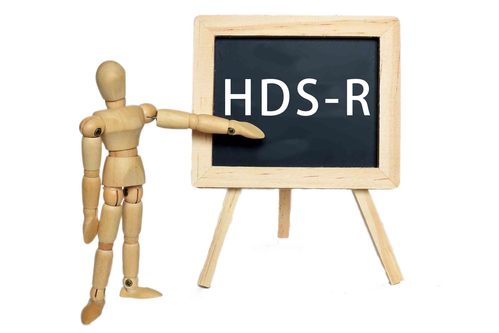
現場ノウハウ
2025/10/14