FIMで知っておきたい排泄コントロール(排尿・排便)の採点方法
現場ノウハウ
2025/10/14
現場ノウハウ
レクリエーション
更新日:2025/05/19
デイサービスなどの介護施設の年間行事予定表を企画していますか?月ごと・季節ごとのお花見・運動会・敬老会・お正月などの行事やイベントの概要、目的や実施方法、注意点などをご紹介します。介護施設では、行事が社会参加や生活意欲の向上に繋がるため、開催に積極的な施設が多いです。デイサービスなどでは機能訓練を兼ねた外出等を企画したり、近隣の住民や保育園・幼稚園の幼児などを招いた催しイベントなど盛んです。
この記事の目次
⇒「わかりやすい介護記録が書ける8つのポイント」資料のダウンロードはこちらから
デイサービスなどの介護施設では、季節感や特別感のある行事やイベントが盛んに取り組まれていて、担当になった職員は企画書やイベント案の作成や司会の依頼などにいろいろ大変かと思います。この記事では、年間行事予定表の参考になりそうな行事を月ごとに提示し、その目的や実施方法、注意点などをご紹介します。レクレーション企画書や行事計画書などにお役立ていただけましたら幸いです。
⇒「わかりやすい介護記録が書ける8つのポイント」資料のダウンロードはこちらから
デイサービス(指定通所介護)は、事業所内でサービスを提供することが原則ですが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものとされています。
| デイサービスの外出レクの注意点と案内文のひな形 デイサービスの外出レクの注意点や案内文の具体例 デイサービスの外出レクでは、運営基準上押させておきたいルールがあります。また、案内文などでご利用者の希望を確認することが望ましいため、こちらの案内文の雛形テンプレートをご活用ください。 |

桜の花見は日本人なら誰でお季節感を楽める行事です。大きな施設だと、敷地内に桜の木があり、施設内で花見ができ、毎年の恒例行事になっていることも多いと思います。小規模の施設や敷地内にお花見ができる樹木がない場合には、近隣のお花見スポットまで歩いていくというケースもあります。この場合には、通所介護計画書に機能訓練を目的とした外出をすることを位置付けた上で、事前に外出計画について周知し同意をいただいた上で行う手順を踏んでお送りするようにしましょう。
※ デイサービスの場合には、サービス提供時間内に「お花見ドライブ」のように機能訓練に関係しないような形で外出することは認められていませんのでご注意を。

端午の節句とは、「菖蒲〔しょうぶ〕の節句」とも言われ、現在のこどもの日です。端午の節句は強い香気で厄を祓う菖蒲をつるしたり、また菖蒲湯に入ることで無病息災を願う催しです。 江戸以降は男の子の節句としての意味合いが強くなり、身を守る鎧や兜を飾り、こいのぼりを立てて成長や立身出世を願ってお祝いとなっています。
デイサービスなどの介護施設では、季節感を出すために、鎧や兜、鯉のぼりを飾ったり、無病息災を願う目的で入浴の時に菖蒲湯で提供したりしたりする行事にしたりしています。
6月は、梅雨の時期でじめじめした季節になります。6月には祝祭日がありませんが、父の日があります。デイサービスなどではなかなか父の日になじみが方もいるかもしれませんが、孫のような世代のスタッフにとってみなさまは尊敬する父のような存在と伝え、感謝の気持ちを込めてメッセージやプレゼントを贈るなどすると喜んでいただけると思います。
6月は夏至があり、1年でもっとも明るい時間が長い日があります。その流れから、節電やスローライフの推進からキャンドルナイトなどを行うイベントが若い人の間で流行りだしました。介護施設ではなかなか難しいかもしれませんが、夕方にキャンドルをたいて、一年でもっとも日が長い1日をキャンドルの少しの時間火で過ごすと特別感が出るかもしれませんね(リスク管理や説明が難しいイベントではあります)

7月といえば、七夕の季節で、介護施設でも6月末頃から竹を飾り、七夕飾りた短冊の製作を通して季節を楽しんでいただくことが多いです。七夕では一般的にお願い事を短冊に書きますが、高齢者の中には非常にネガティブな内容を書いてしまう方もいるので、職員で盛り上げながら書いたりする方が気持ちの良いイベントになるかと思います。

8月は一般的にもお祭りや盆踊りが多い季節です。デイサービスなどの納涼祭では、施設内でレクの時間に行うことも多いですが、大規模な介護施設の納涼祭では、ご家族様と一緒に、夏を楽しみながら地域住民との交流を図るところまで含めて大規模に開催することもあります。また、近年は介護のイメージを変えるため、夏フェスという名称で本当にお祭りや納涼祭を超えた一大イベントのように開催する施設もあります。
納涼祭の内容としては 、施設長挨拶に始まり、職員やボランティア・厨房職員などが焼きそばやかき氷などの簡易的な屋台料理を提供したり、ご利用者が楽しめる輪投げや射的、盆踊りなどを行なったりすることが多いです。衛生管理やリスク管理には十分注意が必要ですが、飲食があるとご家族も気軽に参加でき、盛り上がります。
デイサービスでの通常のサービス提供時間内で、サービスに支障をきたさない範囲で諸条件をクリアすれば、地域や地元のお祭りやイベントの参加もできないわけではありません。幼稚園や保育所のイベント等、至近距離内での行事への参加なども、適切なマネジメントに基づき計画・同意の上、通所介護のサービス提供の一環として、機能訓練等の目的や効果が認められる場合は可能という判断になります。

9月は敬老の日があり、高齢者が多い介護施設では敬老会は重要な行事として位置付けられています。ご家族と共にお祝いしたり、自治体の敬老祝賀会などにお呼ばれできればそれが何よりですが、介護施設では独自に敬老会を主催することが多いです。
敬老会は、名前のとおり、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、その長寿を祝う目的の行事です。近年は、子どもたちもなかなかおじいちゃんおばあちゃんと接することが少ないということで、近隣に保育園や幼児園がある場合には事前に相談すると子どもたちを招待して元気にお歌を歌ったり、プレゼントを手作りしてきてくれたりするかもしれません。
敬老会の内容としては、紫、黄色、白などの色のちゃんちゃんこを着ていただき写真撮影が定番です。
家族懇談会と合わせて実施することでご家族の参加率をあげるなどの工夫もできます。
10月は体育の日があり、一般的にも学校や会社などで運動会を実施することが多い季節です。介護施設というと運動会とは無縁と感じる方もいるかもしれませんが、ご利用者と職員で運動会を実施するととても盛り上がります。施設の一体感や、役割分担による所属欲求を満たすことなどが運動会の目的に挙げられます。
運動会の内容としては、施設長挨拶、来賓挨拶、選手宣誓(ご利用者)、玉入れ、綱引き、職員のダンス、応援合戦、大玉送り、座ったままのリレーバトン渡しなどが定番の流れかと思います。

秋の季節の定番の行事といえば紅葉を見ることですね。食欲の秋ということで、栗ご飯やさつまいもなどと合わせて、紅葉狩り、紅葉見物レクを企画して行事にすると魅力的です。
※ デイサービスの場合には、サービス提供時間内に「紅葉ドライブ」「紅葉ツアー」のように機能訓練に関係しないような形で外出することは認められていませんのでご注意を。
レクリエーション等を行い、クリスマスを楽しんでいただきます。
餅つき:餅つきを行うと共に見学し雰囲気を楽しんでいただきます。
デイサービスを12月31日まで営業するところは限られますが、営業最終日は「今年もありがとうございした!また来年もよろしくお願いします!」という感じで季節感を出すといいですよね!

新年を利用者と共にお祝いします。管理者からの挨拶や、デイサービスの職員やご利用者みんなで新年の抱負などを伝えあったりすると盛り上がります。
1月、新年の行事として初詣をデイサービスで企画することも多いです。やはり日本人なら重要な元旦の行事は1年の幕開けに重要な意味を持ちます。
その場合、施設内に鳥居を立てて、「〇〇デイサービス神社」のような形で行う場合と、機能訓練を兼ねた外出レクとして近隣の神社などに行く場合があります。
デイサービスなどの介護施設では、窒息のリスクのある餅の提供は控えがちですが、餅つきの雰囲気などはぜひ感じてもらいたいものです。口をよく潤し、小さく切って煮込み提供するなどの工夫は必要になります。
1月の季節柄、お正月らしい行事を取り入れるデイサービスが多いです。
書き初め(書道)、福笑い、かるた大会、羽子板、こま回しなど、お正月らしい遊びやイベントを取り入れると季節感を感じてもらえますね!

介護施設では、職員が鬼になり、利用者による豆まきを行うことが多いです。本物の豆を使う場合もあれば、丸めた紙やボールなどを使うケースもありますが、節分の目的としては季節感を感じていただくことと、機能訓練を兼ねることが多いです。

ひな祭りといえば、ひな人形を飾って節句をお祝いする行事です。高齢者になるとお孫さんなどがいない限り直接的に雛人形を飾ってお祝いするイメージはありませんが、雛人形を眺めるとなんとなく気持ちが湧き立つようです。雛人形自体は、女の子が巣立った後に処理に困る方が多いようで、寄付してくださる方も比較的容易に見つかります。
イベントとしては、女の子とがいないとなかなか大々的にやることはなく、何を祝っているのかわからなくなり不発になってしまうかもしれないので、ひなあられをおやつに提供したり、ひな祭り週間などにして雛人形と桃の花を飾ったり…という形で催しを行うのが現実的かもしれません。
季節ごとのイベントは、単なるレクリエーションにとどまらず、高齢者の心身の健康を支える大切な機会です。日々の生活にメリハリを与え、楽しみや役割を持つことが、介護予防や生活意欲の向上に繋がります。ここでは、季節イベントを開催することの主なメリットについて整理します。
季節イベントでは、手作業や身体を動かす活動が多く取り入れられます。例えば、七夕の短冊づくり、運動会の軽体操、クリスマス会でのダンスや合唱などが挙げられます。これらの活動は、自然な形で身体を動かす機会となり、筋力低下や関節が固くなることを防ぐ一助となります。
季節ごとの行事を楽しむことは、生活に彩りを与え、喜びや生きがいの創出につながります。参加することで「自分らしい時間を過ごせた」「楽しい一日だった」と感じる機会が増え、QOL向上に繋がります。
イベントは、利用者同士やスタッフとの交流を深める絶好のチャンスです。共通の話題や体験を通じて自然な会話が生まれ、孤立感の軽減や人間関係の活性化が期待されます。また、ご家族を招いたイベントでは、家族間の絆も強まります。
季節に応じた飾りつけや食事、風習に触れることで、五感を通じた「季節の移ろい」を体感できます。高齢になると外出の機会が減り、季節を感じにくくなることがありますが、施設内での季節イベントにより、その感覚を取り戻し、日々の満足度が高まります。
季節イベントは、高齢者の生活に彩りを与える貴重な機会ですが、配慮を欠くと逆に疲労や不安を招く場合もあります。安心して楽しめるイベントにするためには、利用者一人ひとりの状態や気持ちに寄り添った計画と運営が求められます。ここでは、季節イベントを行う際に特に気をつけたいポイントを整理します。
季節の変わり目は体調を崩しやすく、無理をすると負担になることがあります。イベント当日だけでなく、準備段階から利用者の体調や疲労度に配慮し、参加の可否を柔軟に判断することが大切です。冷暖房の調整や水分補給など、環境面への配慮も忘れずに行いましょう。
過去の経験や性格により、イベントに積極的になれない方もいます。そうした方にも自然に参加してもらえるよう、声かけや役割の提案を工夫しましょう。「見ているだけでもOK」という安心感を与えることも一つの配慮です。
イベント中のやりとりや進行において、利用者を「主役」として尊重する姿勢が重要です。年長者としての人生経験に敬意を払い、上から目線にならない言葉遣いや態度を心がけましょう。記念撮影や作品展示などで個々の努力や参加を讃える場面をつくるのも効果的です。
聴力や認知機能に差があることを前提に、ゆっくりと丁寧な進行を意識します。難しい言葉を避け、視覚的な補助(ホワイトボードやカード)を取り入れると、より多くの方に内容が伝わります。確認の声かけや繰り返しの説明も有効です。
職員自身が楽しんでいる姿は、利用者に安心感や一体感を与えます。イベントは「やらされる業務」ではなく、共に場をつくる時間として捉えることで、自然と良い雰囲気が生まれます。職員の笑顔や積極的な関わりが、イベント全体の雰囲気を左右する大きな要素となります。
季節イベントは多くの高齢者施設で取り入れられている人気の取り組みです。利用者やご家族からのよくある質問に対してわかりやすくお答えします。
レクリエーションは日常的に行われる体操やゲームなどを通して身体や脳の活性化を図る活動です。一方、季節イベントは特定の時期(例:お正月、ひな祭り、夏祭りなど)に合わせた年中行事としての意味合いが強く、非日常感や季節感を楽しむことを目的としています。より特別な演出や装飾、料理などを取り入れることが多いのが特徴です。
必ずしも毎月実施する必要はありませんが、四季の節目に合わせて年間に数回行う施設が多いです。春は花見、夏は納涼祭、秋は敬老会、冬はクリスマス会など、季節ごとの楽しみを取り入れることで、生活にリズムと変化をもたらします。
多くの施設では事前にお知らせした上で、ご家族の参加を歓迎しています。利用者様にとっても、ご家族と一緒に楽しむ時間は大きな励みとなります。ただし、感染症対策や会場の都合により人数制限などが設けられることもありますので、事前の確認が必要です。
施設内にいながら季節感を味わえるよう、装飾や食事、音楽など五感を使った工夫を行います。体を動かすことが難しい方でも、見て楽しめる出し物や飾りつけ、写真撮影などを通じて参加することがあります。
通常の範囲で実施されるイベントに関しては、多くの場合、追加料金はありません。ただし、特別な材料費や外部講師の招へい、豪華な食事の提供などがある場合には、実費相当分を負担する場合もあるので、事前の確認が必要です。
年間行事表のイベントの具体例を紹介しました。実際にはこの他に、研修会、避難訓練、大掃除などもあります。レクの企画はレク係や委員会などで行うケースが多いですが、計画的に行わないと業務負担が大きいです。また、避難訓練や研修などは計画的に行うことが運営基準上必要となります。注意して計画を立ててみましょう!
【関連記事】
▶︎通所介護(デイサービス)の必須法定研修項目の例と実地指導に必要な記録
デイサービスでは職員に研修を受けさせることが運営基準で定められています。高齢者虐待防止法で定められている「身体拘束・高齢者虐待」など、運営基準の各項目に「必要な研修をすること」というような表現で指定されているものです。
▶︎デイサービスの新聞作り ご利用者や家族・ケアマネに喜ばれる広報誌の作り方デイサービスの最新情報や、活動報告として新聞や瓦版などの広報誌を作って定期的に情報発信していることが多くあります。デイサービスの新聞・広報誌のレイアウト・テンプレートの例や作り方を紹介します。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
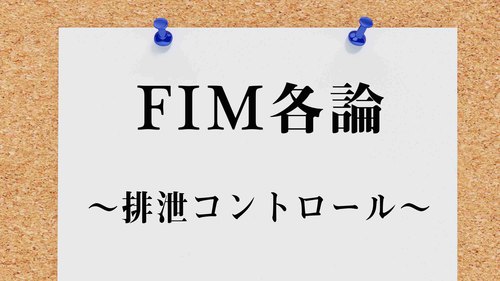
現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14
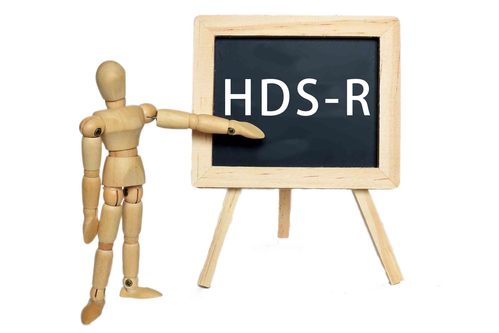
現場ノウハウ
2025/10/14