【2025年12月更新】デイサービス向けの行政最新情報まとめ
介護保険法
2025/12/05
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2025/10/01
【令和6年報酬改定対応】個別機能訓練加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は名称が似ており、要件や単位数の違いが複雑で、混乱している方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、違いや算定要件を、令和6年度の改定内容を反映してわかりやすく解説します。 この記事を読めば、二つの加算の違いが明確に理解できます。
この記事の目次
⇒個別機能訓練加算の計画書作成から機能訓練、日々の書類業務をトータルサポート!<資料をみる>
まず、二つの加算がそれぞれ何を目的としているのか、基本的な役割をおさえましょう。
⇒個別機能訓練加算の計画書作成から機能訓練、日々の書類業務をトータルサポート!<資料をみる>
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の具体的な違いは、主に「目的」「単位数」「人員配置」「LIFE活用の要否」にあります。 令和3年度の改定で、現在の加算(Ⅱ)はLIFE活用に特化した加算として新設されました。
さらに、令和6年度の介護報酬改定では、加算(Ⅰ)ロの単位数と人員配置が変更されています。
【令和6年度の主な変更点】
この章では、令和6年度介護報酬改定以降の個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)それぞれの算定要件を解説していきます。
⇒個別機能訓練加算の計画書作成から機能訓練、日々の書類業務をトータルサポート!<資料をみる>
令和3年度以前の個別機能訓練加算と比較すると、対象や算定要件、機能訓練項目などは同じですが、(Ⅰ)ロは単位数と機能訓練指導員の配置基準が異なります。どちらも個別の機能訓練についての算定要件であり、大きな違いは人員配置のみです。
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | |
|---|---|---|
| 単位 | 56単位 | 76単位 |
| 機能訓練指導員の配置基準 |
常勤・専従を1名以上配置 (配置時間の定めはなし) |
配置時間の定めのない機能訓練指導員2名以上 |
「個別機能訓練加算(Ⅰ)」についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
▶︎個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定要件
機能訓練指導員について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
▶︎機能訓練指導員の仕事内容とは?必要な資格と配置でとれる加算
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していることに加え、厚生労働省に訓練計画の情報提出とフィードバックを受けること(LIFE活用)が必要です。個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する場合は、LIFEを導入して算定したほうが単位数が増えるのはもちろん、科学的介護推進への足掛かりにもなるでしょう。
「個別機能訓練加算(Ⅱ)」についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
▶個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件・単位数とLIFEへの提出方法
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定することが可能です。また、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定が条件です。
同時算定する際は、以下の点に注意しましょう。
最新の令和6年度介護報酬改定より前、令和3年度介護報酬改定までの個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に関しても内容をおさえておきましょう。
まずは、平成30年度改定までの個別機能訓練加算(I)・(II)との大きな違いは、単位数と実施範囲です。個別機能訓練加算(Ⅰ)は、身体機能の維持・向上に関する内容を実施するのに対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)のほうが生活機能の維持・向上の獲得を目的としているため難易度が高く、個別機能訓練加算(Ⅰ)と比べ10単位高く算定できるようになっていました。
また、実施範囲については個別機能訓練加算(Ⅰ)には人数の規定がないのに対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)は5名以下という規定が設けられています。
令和3年度の介護報酬改定により、リハビリに関する要件が個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロとなり、個別機能訓練加算(Ⅱ)の変更点はLIFEへの提出に関する要件だけに変更されています。
今回の令和6年度の介護報酬改定により、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの機能訓練指導員の配置基準が緩和されましたが、単位数が9単位減少しました。
個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)は、同時算定をおこなうことで単位数が増え、事業所の増益につながります。科学的介護の浸透にもつなげることができ、利用者にも事業所にもメリットが多い加算といってよいでしょう。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するにはLIFE活用が必須ですが、今後も科学的介護の推進の一環としてLIFEの活用を広めることが予想されますので、将来的に活用する意味でもLIFEの活用を始めていくことをおすすめします。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。

介護保険法
2025/12/05

介護保険法
2025/11/06
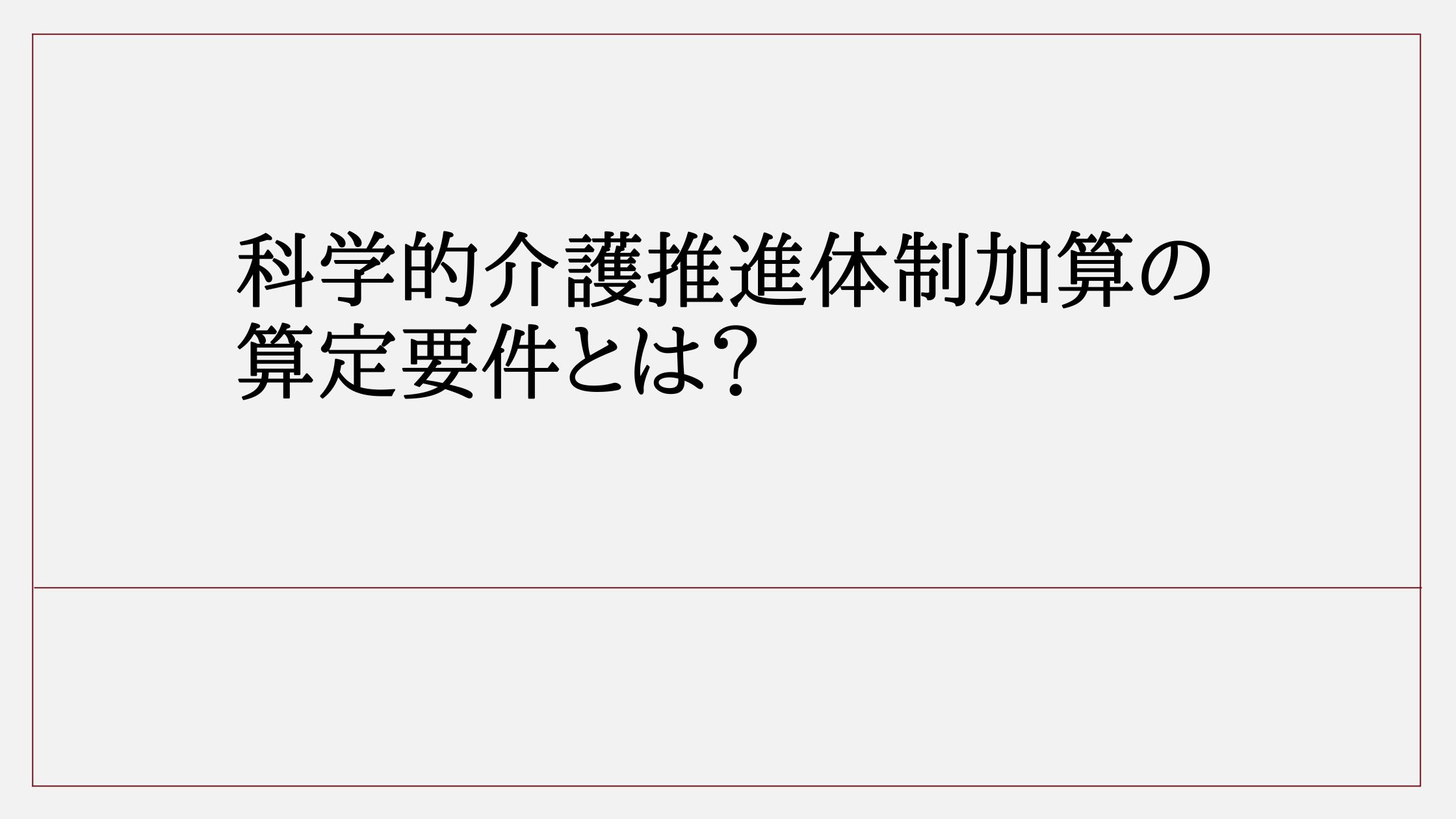
介護保険法
2025/10/24

介護保険法
2025/10/09

介護保険法
2025/10/09

介護保険法
2025/10/09