【令和6年介護報酬改定】LIFE(科学的介護情報システム)の動向|都度更新
介護報酬改定
2025/02/20
介護報酬改定
更新日:2024/09/12
令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬や運営基準はどうなるのでしょうか。最新動向がわかり次第、この記事を更新していきます。令和6年度介護報酬改定について気になる方はぜひご参考ください。
この記事の目次
⇒「令和6年度介護報酬改定の決定事項」解説資料のダウンロードはこちらから
介護報酬改定は、介護報酬の適正化を図るため、国の財政やその時々の社会情勢・環境の変化、介護サービスの事情などを踏まえて、3年に一度のサイクルで行われる見直しのことです。
収益の大部分を介護給付で賄っている介護サービス事業所が多いため、介護報酬改定は決して他人事ではありません。基本報酬の減額で収益減につながる恐れがあり、その反対に新しい加算の創設によって収益増となることも見込めます。
新しいサービス区分の創設や廃止によって施設運営に大きな影響があるため、早めに情報収集し対応策を考えておくことが大切です。
介護分野における介護報酬と同じく定期的に見直しされている社会制度の中に、医療分野の診療報酬があります。介護報酬改定は3年ごと、診療報酬改定は2年ごとに行われているため、2つの報酬改定が重なる「ダブル改定」が6年ごとに訪れます。
介護報酬・医療報酬ともに被保険者からの保険料徴収と税金を財源としており、その財源をもとに介護保険制度では介護サービスの給付、医療保険制度では治療・投薬等の医療サービスが給付されています。
医療保険制度・医療保険制度は全く別々のものではなく、連携体制のもとサービス提供されていると考えて良いでしょう。ダブル改定は連携強化のための大切な機会ととらえて間違いなさそうです。
平成30年度(2018年)のテーマは「医療と介護の連携」でした。医療・介護は施設から在宅や地域でケアしていく、という方針が色濃く出た改訂だったといえるでしょう。
平成30年度(2018年)の介護報酬改定は2017年4月26日から介護給付費分科会で議論が開始され、2018年4月より改定となっています。改定率は介護サービス全体で+0.54%となり、2015年の-2.27%を大きく上回っています。具体的な内容は以下の通りです。
令和6年度(2024年)の改定では、より医療・介護の連携が強化されることが予想されます。介護報酬改定で焦点となるのは以下の項目です。
【緩和・推進される項目】
居宅のケアマネも総合事業(要支援)のプランを扱えるようになる
医療情報と合わせた情報のデータ共有に向けた新しいプラットフォームの推進、各種申請書類の電子化を含むICT化の推進
地域包括支援センターの有資格者配置要件の緩和
【慎重な議論・議論延長されている項目】
要介護認定の有効期間拡大
「介護助手」の法制度上の明確化
特養の要介護1・2受け入れ幅拡大
老健・介護医療院の多床室の室料負担(前向きだが議論延長)
その他給付と負担全体の見直し(議論延長)
令和6年の介護報酬改定の現在決まっているスケジュールは以下の通りです。
【令和5年】
※地方自治体における条例の制定・改正に要する期間を踏まえて、基準に関しては先行してとりまとめを行う。
↓
令和6年度政府予算編成
↓
【令和6年】
過去の介護報酬改定においても同じようなスケジュールで進められており、令和6年においても大幅な流れの変更はないでしょう。
介護報酬改定の全体像が見えてくるのは令和5年の12月ごろになりそうです。
参考:令和6年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)
⇒「令和6年度介護報酬改定の決定事項」解説資料のダウンロードはこちらから
ここでは、令和6年度の介護報酬改定に置ける通所介護・地域密着型通所介護の位置づけや、介護報酬改定の方向性についてご説明します。
令和6年度の介護報酬改定では、令和3年度の介護報酬改定で打ち出された科学的介護の推進が引き継がれ、科学的介護の取り組みがさらに加速します。自立支援介護に向けてケアプランやケアマネジメントの質を向上させるのが大きな狙いです。
居宅介護支援事業所においても、ケアプランの情報を利活用させるためにLIFEの提出が必要になってきます。ケアマネジャーは経験則ではなく、データベースやガイドラインに基づいたケアプランの作成、提出を求められます。
そのためには、他職種が連携してADLを評価するBarthel Index(BI:バーセルインデックス)や認知症の周辺症状を評価するDBD13、口腔・栄養や褥瘡などさまざまな評価を定期的に実施する必要があるでしょう。
また、LIFEへのデータ提出も必須になると考えて間違いなさそうです。利用者の適切なアセスメントと担当者間の共有、フィードバックというPDCAサイクルを循環させるためにも、LIFEの活用は欠かせないといえます。
まずは通所介護・地域密着型介護に関して、令和3年度の介護報酬改定をおさらいしておきましょう。
通所介護は以下のほかに「大規模型Ⅱ」「大規模型Ⅰ」で分けられ、それぞれ報酬単位が決められていますが、いずれの規模でも単位がプラスされ、介護報酬は全体的にアップしています。
中でも地域密着型通所介護の単位増の幅が最も大きくなっています。
| 現行 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 648 | 655 | +7 |
| 要介護2 | 765 | 773 | +8 |
| 要介護3 | 887 | 896 | +9 |
| 要介護4 | 1,008 | 1,018 | +10 |
| 要介護5 | 1,130 | 1,142 | +12 |
| 現行 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 739 | 750 | +11 |
| 要介護2 | 873 | 887 | +14 |
| 要介護3 | 1,012 | 1,028 | +16 |
| 要介護4 | 1,150 | 1,168 | +18 |
| 要介護5 | 1,288 | 1,308 | +20 |
厚生労働省の資料「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護」によると、通所介護の人員基準・設備基準に関しては以下のように記載されています。
人員基準では生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員に関して基準が設けられており、生活相談員又は介護職員のうち一人以上が常勤と定められています。
また、どの事業所でも機能訓練指導員は必ず配置が必要になっており、機能訓練を重視している様子がわかります。
設備基準では、食堂・機能訓練室・相談室が必要な設備と定められており、相談室は内容が漏えいしないよう配慮することが定められています。
食堂・機能訓練室に関しては必要な面積(利用定員×3.0㎡以上)となっていることから、リハビリに十分な広さを確保することが求められているのがわかります。
参考資料:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
厚生労働省の資料「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護」では、現状の課題として以下の点が挙げられています。
◼報酬については、サービス提供時間、要介護度別、事業所規模「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大規模型Ⅱ」に応じた基本報酬が設定されている。※認知症対応型通所介護については、小規模であること、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスであることにより基本報酬を高く設定している。
◼請求事業所数は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成28年度までは増加傾向にあったが、その後はほぼ横ばいである。認知症対応型通所介護については、平成27年度までは増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。
基本報酬の請求事業所は平成28年度までは増加傾向にありましたが、その後はほぼ横ばいです。認知症対応型通所介護については基本報酬を高く設定しているにもかかわらず、平成27年度までは増加傾向、その後は減少傾向に転じています。
請求事業所数がのびていない理由は、デイサービス全体の数がほぼ横ばいであることが関係しているようです。
また、収支についての現状は以下の通りです。
◼収支差率は、令和3年度決算においては、通所介護が1.0%(対令和2年度比△2.8%)、地域密着型通所介護が3.4%(対令和2年度比0.6%)、認知症対応型通所介護が4.4%(対令和2年度比△4.9%)であった。
通所介護は対令和2年度でマイナス、プラスとなった地域密着型通所介護でも対令和2年度0.6%と非常に低い成長率となっており、収支面・経営面でも課題を抱えている可能性が考えられそうです。
令和6年度介護報酬改定関係団体ヒアリングが行われ、通所介護・地域密着型介護に関しては以下の要望が出ています。以下は日本ケアテック協会からの要望です。
1 令和6年度介護報酬改定に関する意見
サービス利用者数の増加の一方、相対的な担い手不足の観点からは、介護事業所・現場が混乱しない形で介護サービスの効率的な提供が不可欠である。そのためには、地域包括ケアについて、ICT、IoTを用いた地域包括ケアDXの推進が必要であり、その推進の観点から令和6年度介護報酬改定において、以下について検討いただきたい
③ ICT連携による質の向上に対する評価(参考:10,15頁)
• 在宅サービス事業者が利用者家族、事業者、各専門職種と情報通信機器を用いて個別にアセスメントやモニタリング、プラン作成等にあたって参照情報とした場合に、質の高いケアにつながるための取り組みとして評価いただきたい④ 事業所のICT推進に向けた評価(参考:16,17頁)
• 導入後の機器、サービス運用を円滑に行うために事前の検討を行うことが必要だが、現場にはそのような担当者は基本的にはおらず、適切なICT運用ができなければ、政府が目指す生産性向上にも寄与しないばかりか、セキュリティリスクを負うことにもつながりかねない。そのため、介護現場でICT導入に係る外部有識者・コンサルタント業務を行うにあたっての補助・助成の仕組みの充実を検討いただきたい• 介護のICT化とケアテック推進に向けては現場の理解と円滑な利用がカギとなるが、管理職・スタッフそれぞれの層にあわせた知識を身に着けることが重要となるため、資格要件の検討と、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等においても評価していくことを検討いただきたい
これらの意見からは、介護現場におけるICT活用が必須になっていることを踏まえ、ICT導入や活用に対する評価・介護報酬の設置をしてほしい、また補助・助成の仕組みを強化してほしいという要望が読み取れます。
事業所のICT推進のためには、それを助ける仕組み・評価する体制が必要と感じているようです。
以下は、一般社団法人全国介護事業者連盟からの要望・一般社団法人日本デイサービス協会の提言になります。
◯通所サービスにおける生活相談員・看護職員の配置要件の見直し(P23)
通所サービスにおける生活相談員・看護職員の配置要件について、人材の効率化の観点から改めて要件見直しの検討をお願いいたします。
◯看護師確保については待遇も高く採用費も含め支出が多い上に確保が難しく、特に定員数の少ない事業者においては負担が大きい実情があります。また、デイサービスでの看護師業務についてはバイタル等の健康チェックと傷の処置等になることが多いですが、過去の国の調査で看護師が専門職として行うべき業務は2割程度で8割の業務は介護士と同じという結果が示されました。この辺りからも、看護師の専門的配置については緩和できると思います。
これらの提言からは、小規模事業者にとって看護師配置が負担になっているということ、業務内容から看護師の専門配置が緩和できるのでは、という要望が読み取れます。
「デイサービスの看護師の仕事内容が8割介護士と同じ」という結果が示されているため、看護師の配置については条件が緩和される動きが出るかもしれません。
令和5年10月11日に開かれた第227回社会保障審議会介護給付費分科会で、令和6年度介護報酬改定に向けて基本的な視点(案)が出ました。
出典:令和6年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)概要 資料2-1(社保審-介護給付費分科会 第227回)
基本的には、多様化する介護ニーズや地域特性に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進、令和3年介護報酬改定から推進されてきた自立支援・重度化防止に資するサービスの提供を引き続き推進していくこと、などが主軸と言えるでしょう。
また、良質なサービス提供と人材確保のため働きやすい職場環境づくりや柔軟なサービス提供の取組みにも言及されています。
現役世代の急速な減少や介護分野からの人材流出がみられる中、総合的な人材確保の取組みは喫緊の課題として考えられているようです。
令和5年11月1日に開かれた財政制度分科会(財務省)では、これまでの介護報酬改定の総括と、これから(令和6年度以降)の提言がなされました。
出典:財務省 財政制度分科会参考資料(令和5年11月1日開催)
財政制度分科会では、介護報酬改定については主に下記3つについての提言がされています。
この中でも特に通所介護に関係の深いところは「担い手の確保」の部分です。
介護現場の生産性向上と業務効率化は、業界全体の喫緊の課題であり、ICT機器・介護ロボットの利活用の上での人員基準の緩和も検討されているところです。
また他の産業に比べ、介護業界においてソフトウェア投資額の伸びが小さいことにも言及されており、業界全体をあげて業務効率化のために取組みたい考えが示されています。
財務省からの提言なので、コストパフォーマンスを最大限に高めるのが重要とされています。これからはこの提言を踏まえた上で介護報酬改定の議論が進んでいくと思われます。
加算については、制度開始から種類が増加し体系が複雑化されたことが課題とされています。算定率ゼロ・算定率の低い加算については前回に引き続き加算の整理が行われる可能性があるでしょう。
通所介護に関係している介護報酬の単位について、以下の通り変更になっています。
【基本報酬部分】
通常規模の7時間以上8時間未満の提供時間であれば、3〜4単位のアップになっています。
例)通常規模 7時間以上8時間未満
要介護1 658 単位(←655単位)
要介護2 777 単位(←773単位)
要介護3 900 単位(←896単位)
要介護4 1,023 単位(←1018単位)
要介護5 1,148 単位(←1142単位)
出典:社保審-介護給付費分科会第239回(R6.1.22)参考資料2-1
【高齢者虐待防止措置未実施減算】
基本単位から1/100減算になっています。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日
【業務継続計画未実施減算】
基本単位から1/100減算(1年間の措置期間あり)になっています。2023年度いっぱいでの措置期間が終了するBCP計画の策定は、2024年度からは必須となります。
この減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、2024年度いっぱいは減算を適用しない方針です。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日
(Ⅰ)ロの加算要件が緩和された結果、単位数は引き下げられた格好です。非常勤の複数の機能訓練指導が在籍するデイサービスでは加算取得しやすくなったとも言えます。
【個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ】
加算要件が緩和され、常勤の機能訓練指導員がいなくても、複数の機能訓練指導員が勤務していれば(Ⅰ)ロの算定が可能となったが、単位数は76単位(←85単位)となり9単位ダウン
出典:社保審-介護給付費分科会第239回(R6.1.22)参考資料2-1
単位数の変更はないものの、現行の要件と比較し、入浴介助に関する研修等が義務付けられることにより、現場での負担は増加すると思われます。
【入浴加算(Ⅰ)の研修義務化】
入浴介助加算の単位数の変更はなし。現行の入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加え、 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日
単位数の変更はありませんが、LIFEの実情や事業者側の事務作業の効率化を考えた変更となっていると思われます。
LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。その他、LIFE関連加算に共通した以下の見直しを実施。
• 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する 。
• 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日
ADL加算も単位数の変更はありませんが、(Ⅱ)の算定要件が厳格化されたため、この加算を取得することがデイサービスとしての差別化の方法にもなりえるのではないかと考えられます。
【ADL維持等加算(Ⅱ)】
ADL利得が2以上→3以上に変更
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日
基本単位に包括化されたため、加算はなくなりました。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1令和6年1月22日
令和5年12月11日に開かれた第235回社会保障審議会介護給付費分科会では、取りまとめに向け令和6年度介護報酬改定審議報告(案)が提示されました。
以下は通所介護・地域密着型介護に関する項目を抜粋しています。
※【】内は対象サービス・介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記
豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化
【通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護★・通所リハビリテーション】
豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等の所要時間について、利用者の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
【全サービス(居宅療養管理指導★を除く)】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和8年3月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととする。
なお、訪問系サービス、居宅介護支援については、令和3年度介護報酬改定において感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もないこと及び非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和8年3月 31 日までの間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、減算を適用しないこととする。
高齢者虐待防止の推進
【全サービス(居宅療養管理指導★、福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★を除く)】
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3 年間の経過措置期間を設けることとする。
また、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化する。
身体的拘束等の適正化の推進
【全サービス(施設系サービス、居住系サービス★を除く)】
身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア 短期入所系サービス、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務づける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づける。
通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護】
通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求めることとする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
【通所介護、通所リハビリテーション★、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。その際、令和6年度末までの経過措置期間を設けることとする。
また、以下の見直しを行う。
ア 職種間の賃金配分について、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ 新加算の配分方法について、 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。
テレワークの取扱い
【全サービス(居宅療養管理指導★を除く)】
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】
就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)については、日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態 なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。 具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを 踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、施設長や指導 職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護★、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、福祉用具貸与★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、療養通所介護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、療養通所介護】
通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。
引用:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)資料2(社保審-介護給付費分科会第 235 回)
令和5年11月27日の介護給付費分科会では、通所介護の送迎について議論されました。
デイサービスを始めとする通所型サービスの送迎の課題として、送迎業務を負担に感じる職員が存在すること、送迎車の運転業務を担う人材の確保の困難さがあります。
また自治体による送迎ルールの解釈が異なることもあったため、送迎の外部委託や、責任の所在を明確にした上で他事業所の利用者との乗り合いも可能とすることなどが議論されました。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第232回)令和5年11月27日 資料6
業務継続計画(BCP)は令和3年度の介護報酬改定の際、策定が義務付けられました。自然災害や感染症発生時にも介護サービスが提供し続けられるようにするのが目的です。
BCPの策定完了・策定中の事業所は8割を越え、BCP策定の経過措置期間の3年間も今年度いっぱいで終了になります。そのため介護給付費分科会ではBCPを策定していない事業所の基本報酬を減算する案が提示されました。
出典:社会保障審議会介護給付費分科会(第232回)令和5年11月27日 資料3
令和5年10月11日に開かれた第227回社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬改定の施行時期が令和6年度4月から6月になるという議題も出ています。
すでに診療報酬の改定は6月1日からということになっています。それに合わせるのか、介護報酬は4月にするのかは今後待たれる議論です。
参考:介護報酬改定の施行時期について 資料3(社会保障審議会 介護給付費分科会 第227回)
引き続き続報をお待ちください。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。

介護報酬改定
2025/02/20

介護報酬改定
2025/02/20

介護報酬改定
2025/02/04

介護報酬改定
2024/11/06
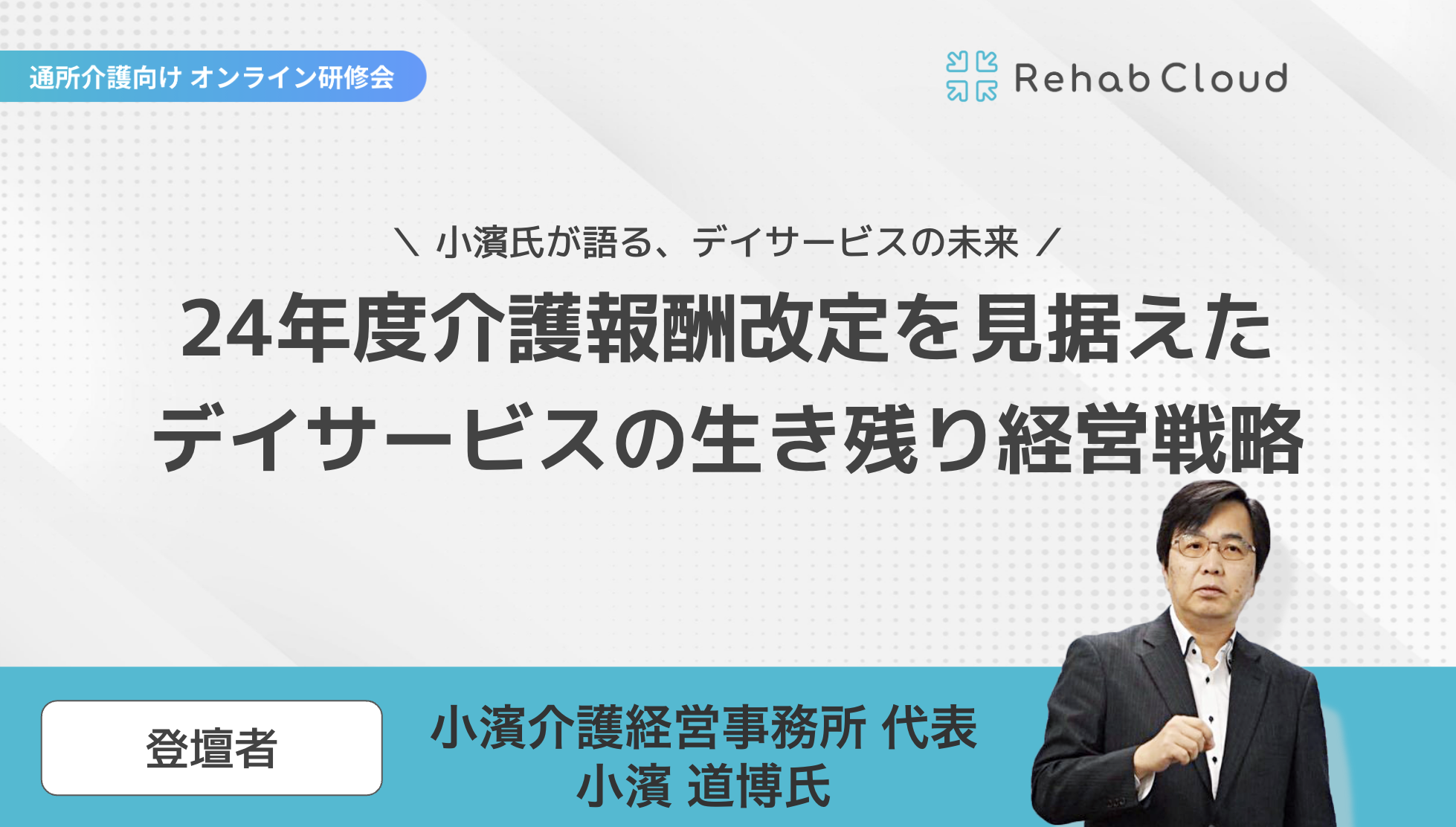
介護報酬改定
2024/10/09

介護報酬改定
2024/10/02