FIMで知っておきたい排泄コントロール(排尿・排便)の採点方法
現場ノウハウ
2025/10/14
現場ノウハウ
介助
更新日:2025/02/26
更衣動作(着替え)は、朝や就寝時、入浴時など日常的に行われる動作です。加齢や病気によって寝たきりなどの介護状態になると身体が思うように動かなくなるため、着替えに介助が必要になります。そんな方々に対してスムーズに更衣介助(着替え介助)を行うためにはどのようなことに注意すればよいのでしょうか?今回は、介護の基礎知識として更衣介助(着替え介助)の準備品や手順と注意点についてご紹介します。
この記事の目次
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

私たちスタッフは、身体が思うように動かなくなった方々に対して着替えの介助(更衣介助)を行います。
その多くは寝たきりの方や介助が必要な方がほどんどです。そのような方々に負担をかけないように、着替えの介助を手際よくスムーズに行うためには事前の準備が重要となります。まずは、更衣介助で事前に準備するものをご紹介します。
【更衣介助で準備するもの】
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

着替えの介助を行う場合に、特に注意していただきたい点について解説します。
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

更衣介助(着替え介助)の中でも、特に寝たきりの方の介助には苦労するのではないでしょうか?
寝たきりの方の更衣介助(着替え介助)を行う場合の手順について「上着の介助」と「ズボンの介助」のそれぞれを解説します。
更衣介助では、基本的にこの順番に沿って介助を行うようにしましょう。
座った状態での更衣介助では、利用者の姿勢の安定を確保しながら、無理なく上着やズボンの着脱を行うことが重要です。特に体幹の支持が難しい方や、麻痺がある方の場合、バランスを崩さないように注意しながら進めましょう。
【上着の介助】
【ズボンの介助】
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる
更衣介助(着替え介助)は、利用者の身体機能や状態に合わせた方法で行うことが重要です。安全かつ快適に衣服を着脱できるように、適切な声かけやサポートを行いながら進めましょう。ここでは、スムーズな更衣介助のポイントを紹介します。
利用者が自分でできる動作を尊重し、できるだけ自身で行ってもらうことで、自立度の維持・向上につながります。介助者は必要なサポートをしながら、利用者のペースに合わせて進めることが大切です。
着脱しやすい前開きの服や伸縮性のある素材を選ぶことで、スムーズな更衣が可能になります。また、ボタンやファスナーの位置が操作しやすいデザインかどうかも重要です。
利用者に安心してもらうために、「次は袖を通しますね」「足を少し上げてください」など、動作の前に声かけを行いましょう。また、利用者の反応を見ながら、無理のないペースで進めることが大切です。
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

ここからは、更衣介助で注意する点について解説していきます。
更衣介助で注意するポイントの1つに『服の着脱の順番』があります。
着替えに介助が必要な方の多くは、身体が麻痺していたり、関節が拘縮(こうしゅく)したり痛みがあったりします。そのような場合に、片側の不自由な側を「患側(かんそく)」と呼び、問題ない側を「健側(けんそく)」と呼びます。この場合に着替えの介助をスムーズにするコツは、『脱ぐときは動きやすい健側から』『着る時は患側から』です。
例えば、右の手に麻痺がある場合は、まず衣服を脱がせる時に左側(健側)の肩から手にかけてゆっくりと脱がしていきます。左側の袖を脱いだら、次に右側(麻痺側)の肩から手を脱がしていきます。
衣類を着るときは、まず右側(麻痺側)から袖を通していきます。その上で左側(健側)から手を通していきます。
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

次に、更衣介助で注意するポイントに『介助する箇所』があります。
麻痺や関節の拘縮(こうしゅく)、痛みがある手足を持ったり、引っ張るように介助をしてしまうと関節を痛みてしまう可能性があります。
着替えの介助を行い場合は、肘や手首などの関節を支えるように介助するようにしましょう。ただし、肘や手首などの骨折により手足の関節を動かすことを禁止されている場合は、関節を持つことは控えましょう。
何より着替えにより痛みがない範囲で、ゆっくりと着替えの介助を行うようにしましょう。
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

次に、更衣介助で注意するポイントに『プライバシーへの配慮』があります。
着替えは、上着やズボンだけでなく肌着や下着などの介助も行います。いくらご高齢者だからといって下の世話をされることは恥じらいがあることです。
カーテンなどでプライバシー保護に努めたり、露出を減らすためにタオルケットを掛けたり、ズボンと上着をそれぞれ順番に行うようにしたりするなど配慮を行いましょう。できることなら、女性のご利用者様であれば女性スタッフが、男性のご利用者様であれば男性スタッフが着替えの介助をするなど同性のスタッフが対応するようにしましょう。

更衣介助は、全身の皮膚状態を観察できる機会でもあります。特に、皮膚が脆弱(ぜいじゃく)なご高齢者の場合は、着替えを行うタイミングで『皮膚の状態をチェック』しておきましょう。
【更衣介助での皮膚状態の観察項目】
褥瘡がある場合は、背中やお尻の衣類にシワがよらないように注意しておきましょう。また、合わせて処方されている塗り薬や貼り薬を交換するのも良いでしょう。
皮膚状態の悪化だけではありませんが、早期発見と早期治療が重要です。そのためには、日頃から着替えの介助を行うスタッフが、対象者の変化に気付けるかが重要なポイントになってくるのではないでしょうか?
| 【関連記事】 高齢者の皮膚トラブルと対処法の考え方について 介護現場で目にする皮膚のトラブルの原因から対策までまとめてご紹介します。 |
⇒記録・書類業務の煩わしさをなくす記録アプリ!資料を見てみる

今回ご紹介したように、着替え(更衣介助)をスムーズに手際よく介助するためには、「事前の準備」と「介助の手順」を理解しておくことが重要となります。
さらに、介助する箇所と皮膚の状態も確認でき、プライバシーも配慮できるスタッフであれば利用者様も安心して着替えを任せることができるのではないでしょうか?
介護・介助の技術は現場の経験値だけでなく、事前に知識を蓄えておくことも重要です。介護のスペシャリストとしての第一歩として参考になれば幸いです。
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「リハブクラウド」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
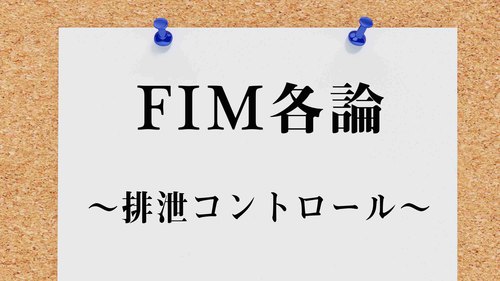
現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14

現場ノウハウ
2025/10/14
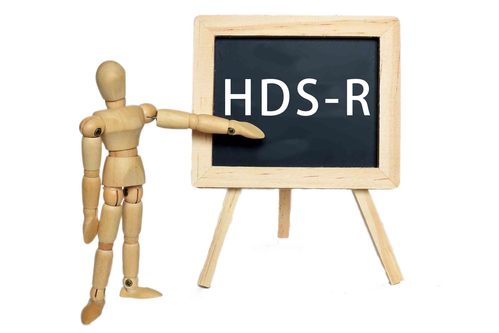
現場ノウハウ
2025/10/14