ICFの「活動と参加」の違い・具体例|介護での書き方・迷った時の考え方
ICF(国際生活機能分類)は、人の「生活機能」と「障害」を捉えるための国際的な枠組みです。特に「参加」の項目を具体的に記述すると、リハビリの課題やケアプランのニーズが明確になり、効果的な介入点を見つけやすくなります。この記事では、ICFの中でも特に混同しやすい「活動」と「参加」の違いや、分類に迷った際の考え方を分かりやすく解説します。
現場ノウハウ
2025/10/09

ICF(国際生活機能分類)は、人の「生活機能」と「障害」を捉えるための国際的な枠組みです。特に「参加」の項目を具体的に記述すると、リハビリの課題やケアプランのニーズが明確になり、効果的な介入点を見つけやすくなります。この記事では、ICFの中でも特に混同しやすい「活動」と「参加」の違いや、分類に迷った際の考え方を分かりやすく解説します。
現場ノウハウ
2025/10/09

バーセルインデックス(BI)の評価場所、自宅と事業所のどちらで悩んでいませんか?通所介護のADL維持等加算で必須のこの評価について、現場で迷うポイントを解説。「できるADL」の考え方に基づき、事業所内での評価で良い理由が明確になります。
現場ノウハウ
2025/10/09

ADLとIADLの違い、正しく説明できますか?介護の基本である2つの日常生活動作について、定義や項目の違いから、FIM・BIなどを用いたアセスメント・評価方法の違いまでを解説。それぞれの訓練内容もわかり、現場での知識が深まります。
現場ノウハウ
2025/10/09

30秒立ち上がりテストは、高齢者の筋力低下を図るスケールとして広がっているテストです。脳卒中患者だけでなく、ロコモやサルコペニア、フレイルなどを検出するテストとしても注目されています。この記事では30秒立ち上がりテストの概要・やり方・カットオフ値などを詳しく解説しています。
現場ノウハウ
2025/09/19

徒手筋力テスト(MMT)とは医療・介護現場で利用される筋力測定スケールのことで、利用者の筋力低下・程度を6段階で評価します。リハビリ計画の立案にも役立つスケールです。この記事では、MMTのやり方や評価表、注意点について解説しています。
現場ノウハウ
2025/09/19

介護現場では必ず「アセスメント」が行われます。利用者の状態・環境把握やその後の介護計画作成のため、事業所の種類を問わず重要な業務です。この記事では介護におけるアセスメントとは何かを紹介しています。
現場ノウハウ
2025/09/18

バイタルチェックとは介護施設や医療機関において、利用者・患者のバイタルサインを測定し異常がないかを確認することです。デイサービスでは利用者が事業所に到着すると、手洗い・うがいを済ませた後、バイタルチェックを行います。ここでは、デイサービスで行われるバイタルチェックの内容や項目、手順などを紹介していきます。
現場ノウハウ
2025/09/18

バランス機能の評価にはどのような評価方法があるか知っていますか?今回は、バランス機能を複合的に評価することができ、信頼性の高いBerg Balance Scale (BBS:バーグバランススケール) の評価方法やカットオフ値についてまとめてご紹介します。高齢者に運動を指導するリハビリスタッフ・機能訓練指導は基礎知識として把握しておくとよいでしょう。
現場ノウハウ
2025/09/18

ADLとQOLの関係性を知っていますか?ADLとQOLの関係についての先行研究から、食事動作ができるほど生活満足感があがることなどがわかっています。ADLは日常生活を送るために必要な基本的な動作のこと、QOLは人間らしく満足した生活を送れているかなどの生活の質を指します。今回は、ご利用者の満足度を高めるために必要なADLとQOLの考え方と関係性について解説します。
現場ノウハウ
2025/09/18
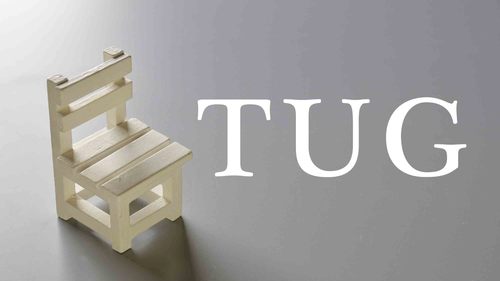
高齢者に行うTUGテスト(タイムアップアンドゴー)とは、バランスや運動器不安定症の検査、転倒リスクの予測として活用される評価方法です。今回はTUGテストで知っておきたい評価方法とカットオフ値(基準値)をご紹介します。これから初めて評価をする方は、基礎知識として参考にしてください。
現場ノウハウ
2025/09/17

握力測定は握力計で簡単に検査でき、他の筋力検査とも相関が高いため、高齢者の筋力を把握するのに大変便利です。医療・介護現場で握力測定を行うスタッフの方は、握力測定の基礎知識を知っておくとよいでしょう。この記事では、握力の測定方法と成人から高齢者までの平均値をご紹介しています。
現場ノウハウ
2025/09/17

認知症テストで知られるMMSE(ミニメンタルステート検査)とは、認知機能の言語的能力や図形的能力(空間認知)を含め、簡易に検査できる30点満点のテストです。今回は、認知症のテストとして世界的に活用されているMMSEの評価方法やカットオフ値、点数(score)の採点ポイントについてご紹介します。
現場ノウハウ
2025/09/11